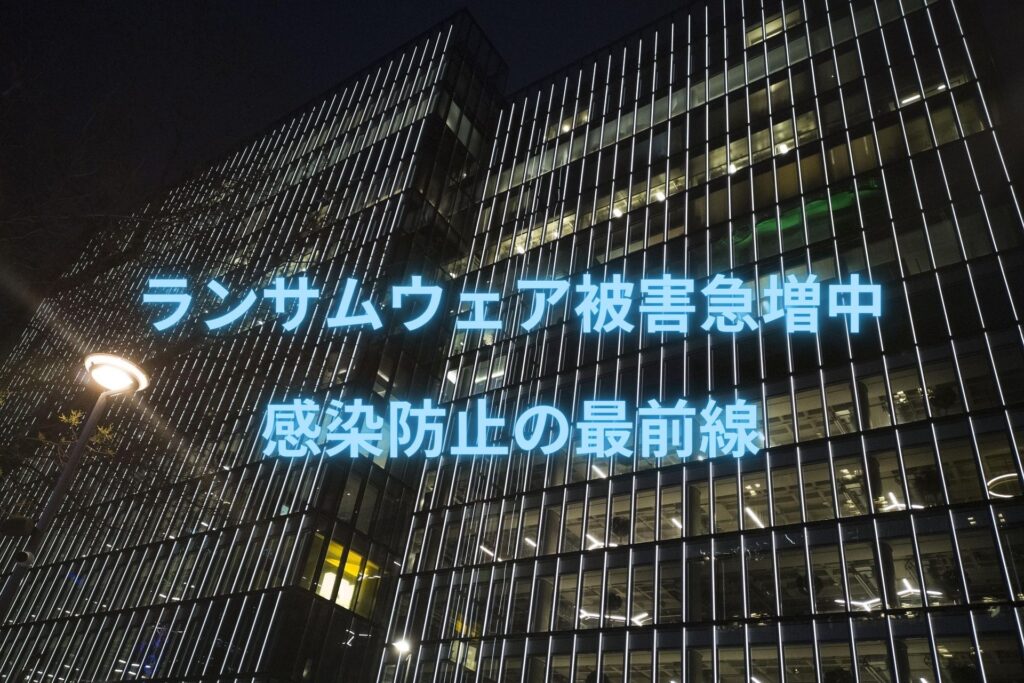ランサムウェアとは?その脅威の本質を知る
ランサムウェア(Ransomware)とは、悪意あるソフトウェア(マルウェア)の一種で、感染したコンピュータやネットワーク内のファイルを暗号化し、復号化のために金銭を要求する攻撃手法です。
近年、ランサムウェアによる被害が急増しており、その影響を受ける組織や個人の数は日に日に増加しています。
感染が拡大する背景には、技術の進化とともにランサムウェア攻撃が巧妙化しているという事実があります。
従来のランサムウェアは単に「ファイルを暗号化して金銭を要求する」ものに過ぎませんでしたが、近年のランサムウェアは、情報を盗む、売買する、または他の犯罪活動に利用するなど、目的が多様化しています。
ランサムウェアの動作原理
ランサムウェアは、感染端末に侵入し、そのシステム内で保存されているファイルをすべて暗号化します。暗号化されると、ファイルを開くことができなくなり、攻撃者はその復号化のために金銭を要求します。支払いを行わない限り、ファイルは復元できないままとなります。従来型のランサムウェアは、感染した端末上でのローカル暗号化が主流でしたが、近年ではクラウドシステムやバックアップサーバーもターゲットにされることが増えており、被害の拡大が懸念されています。
ランサムウェアの攻撃者の目的
ランサムウェア攻撃者の主な目的は、金銭を得ることです。しかし、これにはさまざまな方法が存在します。単純に金銭を要求するものから、企業や政府機関に対する情報戦争の一環として機密情報を盗み取るものまで、多様な手法が取られています。最も一般的なのは、感染端末の暗号化後に金銭の要求を行うというものですが、最近では「データ漏洩」型と呼ばれる攻撃も増加しており、データの公開をちらつかせることで被害者に金銭を支払わせる手口が増えてきています。
感染経路の多様化と巧妙化する手口

ランサムウェアが感染する経路は年々多様化しており、その手口もますます巧妙化しています。従来のメールの添付ファイルや不正なリンクから、最近ではサプライチェーン攻撃やリモートデスクトップの脆弱性を突いた手法も増えてきています。企業や個人が油断している隙を突いて、感染経路を特定するのが難しくなっています。
メールや不正リンクを利用した感染
ランサムウェアの代表的な感染経路として「フィッシングメール」が挙げられます。攻撃者は、受信者が信頼できる送信者から送られたかのように見せかけたメールを送り、その中に含まれるリンクや添付ファイルをクリックさせます。このリンクをクリックすることで、ランサムウェアがダウンロードされ、システム内に侵入します。フィッシング攻撃は、巧妙に企業の信頼できるメールアドレスを偽装したり、危険性が少ないように見せかけたりするため、ユーザーが気づかずにリンクをクリックしてしまうことが多いです。
サプライチェーン攻撃
サプライチェーン攻撃は、第三者の企業やサービスを経由して、ターゲット企業に感染を拡げる手法です。攻撃者は、企業の取引先やサプライヤーに感染を広げ、その後、取引先経由でターゲット企業に感染させます。この手法では、企業の信頼する外部業者を経由するため、非常に気づきにくいという特徴があります。
リモートデスクトップの脆弱性
リモートデスクトップを利用している企業では、サイバー攻撃者がリモートデスクトップの脆弱性を突いて不正アクセスし、システム内にランサムウェアを送り込むケースも増えています。これに対策を怠ると、外部からのアクセスが容易になり、深刻な被害に繋がる可能性があります。特に、強固なパスワードを設定せず、セキュリティ対策を講じていない場合は、攻撃を受けるリスクが高まります。
企業が陥りやすい脆弱ポイントとは

企業のセキュリティ対策が不十分である場合、ランサムウェアに感染するリスクは高まります。特に、業務効率を優先してセキュリティが疎かにされがちな部分には脆弱性が潜んでいます。多くの企業が直面している問題は、セキュリティ対策を施すにはコストがかかることです。しかし、コストを削減しすぎることが結果的に大きな被害を招くことになります。
ソフトウェアの更新不足
企業内で使用しているソフトウェアやシステムが最新のセキュリティパッチを適用していないと、脆弱性が放置されたままとなります。ランサムウェアは、古いソフトウェアや未更新のシステムの隙間を狙って侵入します。企業の多くは、ソフトウェアの更新作業を後回しにする傾向があり、このことがセキュリティリスクを高めています。
セキュリティ意識の低さ
従業員のセキュリティに対する認識が低いと、個人の判断で危険なリンクをクリックしたり、不正なUSBメモリを接続したりするリスクがあります。多くの企業では、セキュリティ教育が不十分であるため、従業員が意識的にセキュリティを守るための行動を取らないことがあります。
バックアップの不備
バックアップを取らない、またはバックアップが不完全な状態で運用している企業は、ランサムウェアに感染した場合にデータ復旧が困難になります。ランサムウェアはデータを暗号化するため、復旧のためのバックアップがなければ事業継続が困難になります。
感染後の対応フローと、やってはいけないこと
ランサムウェアに感染した場合、迅速かつ冷静に対応することが求められます。感染後の対応が遅れると、被害は拡大し、復旧の難易度が増します。感染後に最も重要なことは、適切な行動をとることです。しかし、誤った対応を取ってしまうと、事態がさらに悪化することもあります。
すぐにネットワークを切断
感染が疑われた場合、まず最初に行うべきことはネットワークから切り離すことです。感染した端末がネットワークに接続されていると、他の端末にもウイルスが拡散してしまうため、感染拡大を防ぐためにも即座にネットワークから切断する必要があります。
攻撃者に金銭を支払わない
ランサムウェアの攻撃者が要求する金銭を支払うことは、被害の拡大を招く可能性があります。金銭を支払うことでデータが復旧する保証はなく、さらに攻撃者に「支払いをしても問題ない」と判断され、再度攻撃されるリスクも高まります。
専門家に相談する
感染が確認された場合、できるだけ早くサイバーセキュリティの専門家に相談することが重要です。専門家は、感染拡大の防止や、データ復旧のための最適な手段を提供してくれるでしょう。
セキュリティ強化のための実践的な予防策
ランサムウェアの感染を防ぐためには、予防策を講じることが最も重要です。セキュリティを強化するためには、日々の業務の中で意識的に対策を取ることが求められます。
ファイアウォールとアンチウイルスの導入
企業や個人のネットワークには、強固なファイアウォールとアンチウイルスソフトウェアを導入することが基本です。これらは、外部からの不正アクセスやウイルス感染を防ぐために必要不可欠なツールです。ファイアウォールは、インターネットと内部ネットワークの間でデータの流れを監視し、悪意のある通信を遮断します。
ソフトウェアとシステムの定期的な更新
全てのソフトウェアやシステムは、定期的に最新のパッチを適用し、脆弱性を修正することが求められます。特に、オペレーティングシステムや重要な業務アプリケーションには、必ずセキュリティパッチを適用することが重要です。
バックアップの実施
データのバックアップを定期的に行い、暗号化されていない状態でバックアップを保存することが予防策の一環です。万が一ランサムウェアに感染しても、バックアップがあれば事業の継続性を確保できます。
サイバー攻撃のトレンドと最新の被害事例

サイバー攻撃は日々進化しており、ランサムウェアも例外ではありません。最新のサイバー攻撃のトレンドや実際の被害事例を把握することで、どのような攻撃に対して備えを強化すべきかを理解することができます。
最新のランサムウェア攻撃事例
最近のランサムウェア攻撃では、企業や団体がターゲットにされることが増えており、特に医療機関や政府機関、インフラ関連の企業が被害を受けている事例が目立ちます。こうした攻撃者は、データを暗号化するだけでなく、盗んだ情報を公開する脅しをかけてきます。
攻撃者の手口の進化
現在のランサムウェア攻撃者は、単に金銭を要求するだけでなく、データを盗むことで「データリーク攻撃」に発展することが増えてきました。これにより、攻撃者は情報を公開して企業の信用を傷つけるだけでなく、機密情報の漏洩が社会的な問題に発展するリスクも高まっています。
社内教育と意識改革が未来を守る
ランサムウェアを防ぐために最も大切なのは、社員一人一人がセキュリティをしっかりと意識することです。どれだけ最新の技術を導入しても、社員が注意を払っていなければ、攻撃者に隙を与えてしまいます。
1. 従業員教育の必要性
まず、社員がランサムウェアの危険性を理解することが大切です。例えば、「フィッシングメールに注意する」「怪しいリンクをクリックしない」「不明な添付ファイルを開かない」といった基本的なルールを、定期的に教えることが重要です。
実際の攻撃事例を紹介したり、実際に使われる手口をシミュレーションすることで、社員が「こういうことが起きるかもしれない」と意識できるようにします。
2. 実際の事例を学ぶ
教育の中で、実際にどれくらいの企業がランサムウェア攻撃を受けたか、その結果どうなったかを紹介するのが効果的です。具体的な被害を知ることで、社員は「もし自分たちの会社でも起きたらどうなるだろう?」と考え、危機感を持つようになります。
3. セキュリティ意識を文化として根付かせる
セキュリティは一度教えて終わりではありません。継続的に学び、社内の全員が常に意識するようにすることが大事です。例えば、定期的なトレーニングやチェックを行い、社員が積極的にセキュリティ対策を実践するように仕向けます。
まとめ:対策は「今すぐ」が鉄則

ランサムウェアの被害は、後回しにしていては防げません。早期に対策を取ることが、最も重要です。では、具体的にどうすれば良いのか?というポイントを簡単にまとめます。
1. 迅速な対応がカギ
もしランサムウェア攻撃が発生したら、すぐに問題を見つけて、広がらないように手を打つことが大事です。そのためには、日頃から「攻撃を受けた時にどうするか」を社員全員が把握しておく必要があります。
例えば、怪しいメールを見つけたらどうすべきか、システムの異常に気づいたら誰に連絡するかを、あらかじめ決めておくことが大切です。
2. 対策は一度きりではなく、継続的に
セキュリティ対策は一度やっただけでは足りません。攻撃者の手口は日々進化しているので、常に最新のセキュリティ対策を維持し、更新し続ける必要があります。
例えば、定期的にソフトウェアのアップデートを行うことや、システムの脆弱性をチェックすることが効果的です。また、社員教育も定期的に行うことで、いつでも最新の情報に対応できるようになります。
3. 今すぐ対策を始めよう
「攻撃が発生してからでは遅い」と覚えておくことが重要です。攻撃を防ぐためには、早期に準備をし、対策を講じることが必須です。セキュリティ対策は後回しにせず、今すぐ始めましょう。安全を守るためには、日々の小さな対策が積み重なって大きな効果を生むからです。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。