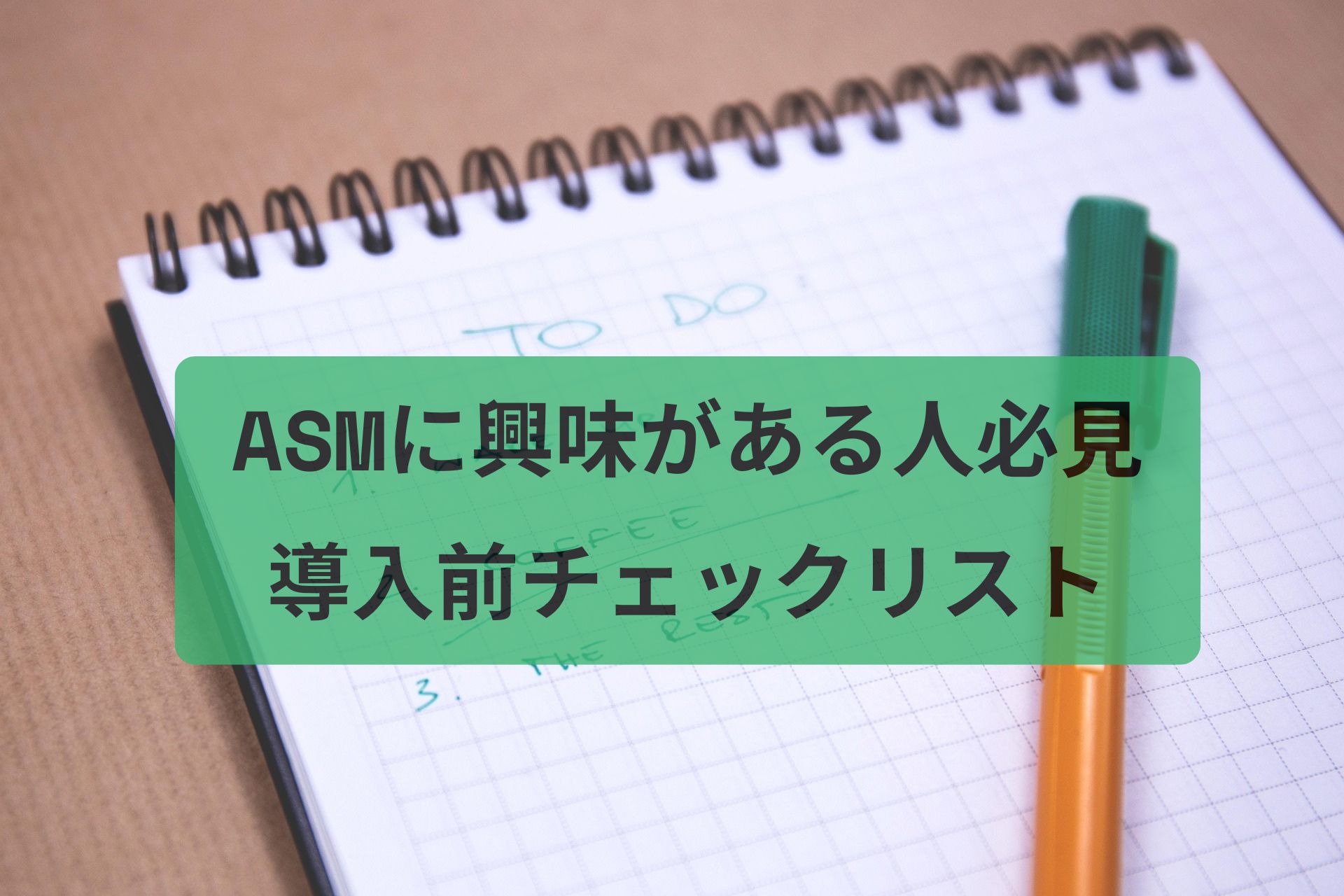サイバー攻撃の高度化とともに注目される「ASM(アタックサーフェスマネジメント)」は、企業にとって次世代のセキュリティ戦略の鍵を握る存在になりつつあります。
とくに経済産業省が公表したガイドラインを受け、ASMの導入を急ぐ企業や自治体が増え始めており、「まずは調べてみたい」という声が多く聞かれるようになりました。
しかし、ASMは単なるツールではなく、セキュリティ体制の根本的な見直しを伴う「取り組み」です。
導入すればそれで終わりではなく、日々の運用・監視・改善が継続的に求められます。
本記事では、ASMの基本的な概念から、導入前に確認しておくべき組織体制や運用面のポイント、ツール選定の注意点、そしてありがちな失敗までを網羅的に整理しました。
ASMの検討段階にある情報システム部門やセキュリティ担当者が、どのような手順で導入を進めるべきかが明確になる構成となっております。
自社にとってASMは必要なのか、導入のハードルは何か、どこから着手すればよいのか。
そうした疑問に答えるための「導入前チェックリスト」として、ぜひご活用いただければと思います。
ASM導入が注目される背景とは

近年、サイバー攻撃の脅威はかつてないほど多様化し、複雑化しています。
標的型攻撃やランサムウェア、サプライチェーン攻撃など、企業を取り巻く脅威は日々進化しており、防御の前提条件そのものが変わりつつあるといえます。
このような背景のもとで登場したのが、ASM(アタックサーフェスマネジメント)です。
ASMは、企業がインターネット上に公開している資産、つまり「攻撃対象となりうる全ての外部資産」を洗い出し、可視化し、管理するためのセキュリティ戦略です。
注目すべきは、その“攻撃対象領域”が企業自身では気づかないままに広がっているという事実です。
たとえば、過去のキャンペーンで使用したドメインが放置されたままだったり、個別に立てられたクラウド環境の設定ミスによって情報が外部に公開されていたりと、無意識の“盲点”が数多く存在しています。
また、リモートワークの定着、クラウドシフトの加速、業務のDX化などが進む中で、管理外の資産(シャドーIT)が増加し、従来型の境界防御では対応できなくなっています。
攻撃者はこれらの見落とされた資産を狙い、入口を見つけ、侵入の糸口にしていきます。
そのような事態を防ぐには、企業が自ら「どこが狙われているのか」「どう見られているのか」を知ることが不可欠です。
ASMはまさに、外部の視点で企業の“攻撃されやすさ”を客観的に把握する仕組みであり、こうした背景のなかで注目が高まっているのです。
経済産業省は2023年にASMに関するガイドラインを発表し、業界問わず対応を促しています。
これにより、今後ASMの導入は“あれば便利”から“ないと困る”時代へと変わっていくと考えられるでしょう。
ASM(アタックサーフェスマネジメント)とは何か
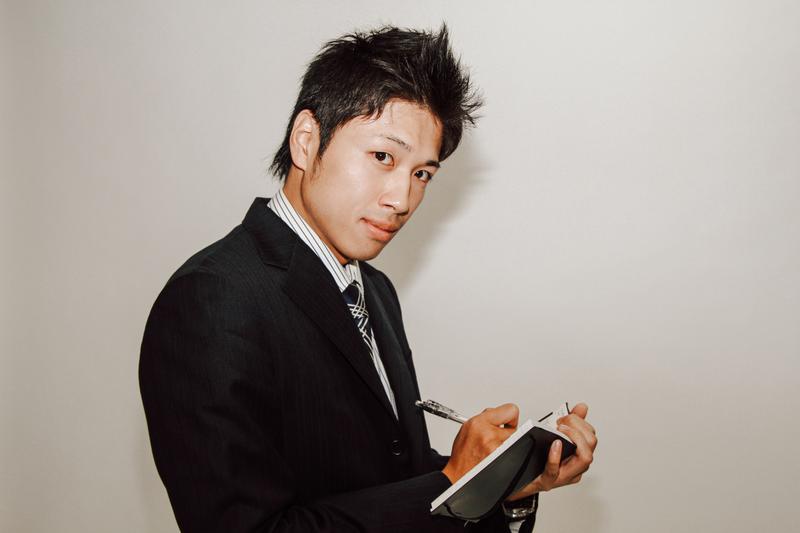
ASM(Attack Surface Management)とは、企業が保有する公開資産を外部からスキャン・監視し、どこにリスクが潜んでいるかを可視化するプロセス全体を指します。
その本質は、「企業自身が把握していない“攻撃対象”を知ること」にあります。
攻撃者の視点に立ち、組織の外部公開資産(IPアドレス、ドメイン、サーバー、SaaSなど)を洗い出し、それがどのように見えているのかを明らかにします。
これにより、企業の“盲点”や“管理外資産”の存在に気づくことができ、事前にリスクを潰すことが可能になります。
たとえば、廃止されたはずのサーバーがインターネットに接続されたままだったり、開発環境のまま放置されたテストサイトが公開されていたりといった例は少なくありません。
これらはすべて、攻撃者にとっては格好の侵入口です。
ASMでは、以下の3つの要素が柱となります。
- 資産の検出:外部に存在する自社関連資産の洗い出し
- リスクの評価:発見された資産に潜むリスクを自動分析
- 継続的監視:変更や新たな資産をリアルタイムに追跡
このように、ASMは単なる“棚卸し”ではなく、「継続的な観測と対応」が求められる領域です。
企業が攻撃を受ける前にその“露出”を減らすことができる、いわば予防医療的なセキュリティ対策だといえるでしょう。
また、ASMはゼロトラスト戦略とも親和性が高く、境界のない世界における新たなリスク管理手法として注目を集めています。
単体で完結するツールではなく、他のセキュリティ製品やプロセスと組み合わせて全体最適を図ることが、今後の主流になっていくと考えられます。
ASM導入前に確認すべき社内体制と課題
ASMを導入するうえで最も軽視されがちなのが、「社内体制の整備」です。
多くの企業が“とりあえず導入”を先行させてしまい、運用フェーズに入ってから「誰が見るのか」「どう対処するのか」が曖昧なまま形骸化してしまうケースが後を絶ちません。
ASMは単なるレポーティングツールではなく、実際の運用に乗せてナレッジを蓄積していく必要がある“サイクル型の管理領域”です。
そのため、導入前に以下のような体制面の整備が必要です。
- 責任部署の明確化:スキャン結果をレビュー・評価するのは誰か
- 連携体制の確保:CSIRTや情報システム部門との即応体制の構築
- ナレッジ共有の設計:拠点間・部署間での情報伝達と履歴管理
- スケジューリング:月次・週次で何をチェックし、誰が報告するか
また、ASMを活用するにはある程度のセキュリティリテラシーが求められます。
ツールの出力結果を正確に解釈し、緊急性を見極めるスキルがないと、誤検知や対応漏れが発生しやすくなります。
この点において、専門性の高い人材が不足している場合には、外部パートナーとの協働体制を整える選択肢も現実的です。
たとえば、マネージドASMサービスを活用し、スキャンと分析の部分はアウトソースし、最終判断と対応を社内で実施するというハイブリッドな体制が近年増えています。
さらに、ASMの運用には定期的なアップデートと振り返りが欠かせません。
環境の変化やビジネス拡張に伴って新たな資産が生まれるため、「一度設定すれば終わり」ではなく、継続的に棚卸しとリスク評価を実施する体制が求められるのです。
導入前には、こうした運用設計・体制構築の準備をしっかりと行い、“ASMありき”ではなく“ASMを活かせる土壌があるか”を確認することが、成功の鍵といえるでしょう。
ASMサービスの選定ポイントと導入パターン

ASMソリューションはベンダーごとに機能・対象資産・連携性が大きく異なります。
そのため、「導入してから後悔する」ことを防ぐためにも、自社の利用目的やリソース状況に合ったサービスを見極める必要があります。
まず確認すべきは、可視化の対象範囲です。
一部のASMはWebサイトやIPアドレスに特化している一方、クラウドストレージ、SaaS、IoT資産、DNS設定など広範に対応しているサービスもあります。
自社のビジネスモデルやIT構成に照らし、どの資産をカバーすべきかを整理することが重要です。
次に、アラートの品質とレポートの見やすさも重要です。
ASMは継続的に通知を受ける運用になるため、誤検知が多いと現場の信頼が失われます。
また、レポート内容が抽象的すぎたり、専門的すぎたりすると、部門間での共有や経営報告が難しくなります。
さらに、他のセキュリティ基盤との連携性も評価ポイントです。
SIEM(Security Information and Event Management)やSOARとの接続が可能であれば、監視データを横断的に活用できます。
API連携、ログ出力、Webhooksの対応状況も含めて、将来的な拡張性をチェックしましょう。
導入形態についても、以下のような選択肢があります。
- SaaS型:導入が容易で初期費用が安い。自動更新や外部保守に優れる。
- オンプレ型:独自要件への対応が可能。セキュリティ要件が厳しい企業向け。
- マネージド型:監視・通知・一次対応まで含まれる。人材不足を補いやすい。
選定にあたっては、単に“機能の多さ”ではなく、“自社で無理なく運用できるかどうか”という視点を最重視すべきです。
ASMは継続運用が前提のため、導入時だけでなく“半年後・1年後にどう使われているか”までを見据えて、サービスを選定することが成功への近道といえるでしょう。
ASM運用の落とし穴と失敗しない実装法
ASMは導入するだけで効果が出るものではなく、“導入後にどのように活用するか”が成果を分けます。
しかし現場では、ASMをうまく運用できていない事例も多く見られます。
その理由は、多くが「人とプロセス」の不足に起因しています。
たとえば以下のような失敗例があります。
- アラートを受け取っても誰も対応せず放置される
- スキャン結果が毎回似ているため“惰性でスルー”される
- そもそもスキャン対象の棚卸しが不完全なまま導入された
- レポートの内容が理解されず、関係者がノータッチ
こうした事態を防ぐには、まずスキャン対象の精査と目的の明確化が必須です。
「何を守りたいのか」「どこまでカバーするのか」を言語化し、体制と仕組みに落とし込むことで、初めてASMの効果が定着します。
また、運用プロセスの自動化・定型化も鍵となります。
アラートに優先順位を設定し、内容ごとにエスカレーションルールを明確化する。
定期的にスキャン結果を関係部門とレビューし、改善策を記録する。
こうした小さな仕組みの積み重ねが、ASMを“使われるシステム”に変えていくのです。
加えて、経営層の関与も無視できません。
ASMによって可視化されたリスクを“経営リスク”とみなして投資判断を下せるようにすることで、ASMの位置付けが曖昧にならず、継続性と重要性が担保されます。
ASMはツールでありながら、組織文化やプロセスにも影響する“構造変革型の施策”です。
それゆえ、単なるITプロジェクトではなく、**「全社的な変革活動」**として捉えることが、運用失敗を防ぐ第一歩といえるでしょう。
まとめ:ASM導入前に押さえるべき最終チェック項目

ASMは、企業の攻撃対象資産を洗い出し、リスクを可視化するという点で非常に強力なセキュリティ施策ですが、その効果を最大限に引き出すには、導入前の準備が不可欠です。
最後に、ASM導入前に確認しておきたいチェック項目を整理しておきましょう。
- どの資産(IP、ドメイン、SaaSなど)を監視対象とするか定義しているか
- システム部門・セキュリティ部門・経営層でASMの目的が共有されているか
- スキャン結果のレビュー・対応を担う体制があるか
- 他のセキュリティ施策(EDR、脆弱性診断、SOCなど)との役割分担が明確か
- ASMのスケジューリング(週次・月次)と改善サイクルを設計しているか
- 必要に応じて外部支援(ベンダー、MSSPなど)との連携体制があるか
これらを一つずつ確認することで、ASMが単なる「導入しただけ」のツールではなく、「実効性あるリスク対策」として機能し続ける土台が整います。
ASMは、攻撃される前に“見えないリスク”を潰すための武器です。
導入によって得られるのは安心感ではなく、「どこに問題があるのかを見極める眼」といえるでしょう。
そうした視点を持った企業こそが、今後のセキュリティレベル競争の中で優位に立つことが期待されます。
ASMは単なるトレンドではなく、これからの“標準装備”となっていくと考えられます。
その第一歩を踏み出すために、ぜひ本記事のチェックリストを実践の起点としていただければ幸いです。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。