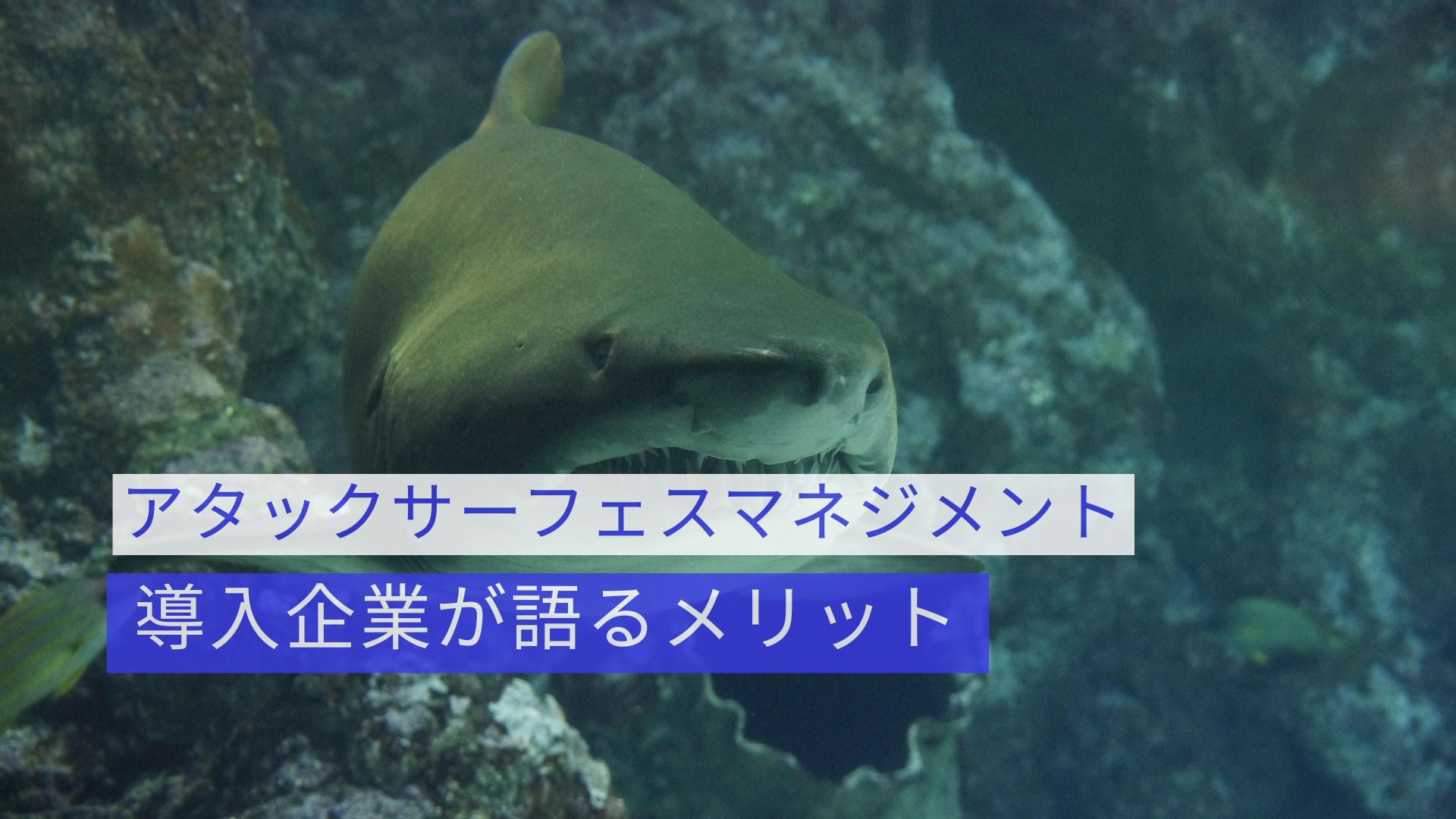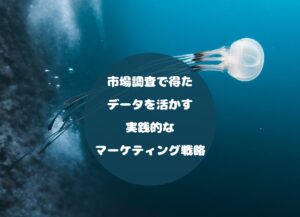近年、サイバー攻撃の手法はますます巧妙化し、企業のIT資産全体が常に脅威にさらされています。
特にクラウドの普及やリモートワークの定着により、従来の境界型防御ではカバーしきれない「攻撃対象領域(Attack Surface)」が広がりを見せています。
この変化に対応するため、多くの企業が注目しているのが「アタックサーフェスマネジメント(ASM)」という新しい概念です。
ASMは、自社のIT資産がどのように攻撃者から見えているかを可視化し、脆弱性やリスクを事前に把握するための仕組みです。
従来のセキュリティ対策では「守るべきもの」が曖昧であったのに対し、ASMでは「見えているもの」=「狙われる可能性のあるもの」を明確化できます。
本記事では、ASMの基本的な仕組みから導入企業の具体的なメリット、さらには副次的な効果や導入時の課題までを、実例を交えて詳しく解説していきます。
ASMの導入を検討している企業の担当者の方にとって、意思決定の一助となる情報を得られる内容となっています。
ASMがなぜ今必要とされているのか、その真の価値を掘り下げていきましょう。
なぜ今、アタックサーフェスマネジメントが求められているのか
アタックサーフェスマネジメント(ASM)が注目される背景には、企業のITインフラを取り巻く環境の大きな変化があります。
近年、クラウドサービスの普及、リモートワークの拡大、そしてSaaSやBYOD(私物端末の業務利用)の増加により、従来の社内ネットワーク中心のセキュリティ対策では、もはや守りきれない状況が生まれています。
こうした分散型のIT環境において、企業の「攻撃対象領域(Attack Surface)」は想像以上に広がっており、管理者が把握しきれないリスクが急増しているのです。
これまで多くの企業は、ファイアウォールやウイルス対策ソフトなどの境界防御型の対策に依存していました。
しかし攻撃者はすでに、このような防御をかいくぐる手法を多様化させており、例えばWebアプリケーションの設定ミス、放置されたサブドメイン、漏洩した認証情報など、「企業が自覚していない脆弱ポイント」を狙うようになっています。
実際、近年のサイバー攻撃事例を見ても、内部システムではなく、外部に露出していたクラウドストレージやWebサービスが攻撃の突破口となっているケースが増えています。
このような状況下で、企業が本当に守るべきなのは「既知の範囲」ではなく、「実際に外部から見えている範囲」だと再定義されつつあります。
つまり、従来型の「守る対象」から、「見えている対象」へと視点を変える必要があるのです。
そのアプローチを実現するのが、まさにASMの役割といえるでしょう。
ASMは、企業の攻撃対象領域を外部視点で常時モニタリングし、資産の棚卸し、脆弱性の発見、構成ミスの検知などを通じて、リスクを可視化します。
そのため、セキュリティ担当者は潜在的なリスクを把握したうえで、優先度に基づく対応が可能になります。
結果として、セキュリティの「見落とし」をなくし、組織全体のリスク耐性を高めることができるのです。
また、外部からの評価という意味では、取引先やステークホルダーからの信頼にも影響します。
セキュリティ監査や情報開示の場面で、「ASMによって継続的に攻撃対象領域を管理している」という事実は、企業の信頼性を高める根拠となり得ます。
このように、ASMの導入は単なる技術的対策にとどまらず、企業のガバナンスやブランディングにも好影響を及ぼすのです。
加えて、政府や業界団体もASMの重要性を明確に打ち出しています。
経済産業省のガイドラインや各種ホワイトペーパーでは、ASMをゼロトラストやEDRと並ぶ次世代セキュリティ戦略の一環と位置づけており、今後はさらに普及が進むことが予想されます。
こうした時代背景を踏まえると、ASMの導入は「選択肢」ではなく「必須」といっても過言ではありません。
単に脆弱性を見つけるだけでなく、攻撃者の目線を自社が持つことによって、より高度な防御が実現できるようになるからです。
ASMは、企業がこれまで見落としていた“本当のリスク”を明らかにし、セキュリティ戦略の再構築を迫る存在となっています。
現代の複雑なIT環境に対応するうえで、避けては通れないテーマであることは間違いないといえるでしょう。
アタックサーフェスマネジメントの基本的な役割と機能とは

アタックサーフェスマネジメント(ASM)は、企業のIT資産が外部からどのように見えているのかを把握し、潜在的なセキュリティリスクを明らかにするための仕組みです。
従来のセキュリティ対策は、既知のネットワークやサーバーを対象にしたものでしたが、ASMは「未知」や「見逃されがち」な資産にも焦点を当てます。
そのため、企業が本当に守るべき範囲を明確にするという、極めて本質的な役割を担っています。
ASMの基本的な機能は、大きく分けて以下の4つに整理できます。
1つ目は「資産の自動検出」です。
ASMは、インターネット上に存在する自社関連のドメイン、IPアドレス、サーバー、Webアプリケーションなどを自動的にスキャンし、一覧化します。
このとき、社内で管理されていない“シャドーIT”や、外部ベンダーが構築した一時的な環境など、通常のIT資産管理ツールでは見落とされる対象も含まれる点が重要です。
2つ目は「攻撃対象領域の可視化」です。
検出されたIT資産がどのような構成になっているのか、どのようなリスクがあるのかを評価し、ダッシュボード上で一元的に表示します。
これにより、担当者は「どこに、どの程度のリスクがあるか」を定量的に把握できます。
特に、日々変化するクラウドインフラやSaaSアカウントの利用状況に対して、継続的な追跡が可能になる点は、既存のセキュリティソリューションにはない特長です。
3つ目は「脆弱性の発見と分類」です。
ASMは、外部からアクセス可能なサービスに対し、既知の脆弱性の有無、構成ミス、SSL証明書の失効などをチェックします。
この際、CVSSスコアや影響範囲に基づいて優先度を自動判定する機能も備わっており、実際のセキュリティ対応に直結する情報を提供します。
また、Zero-Day(未公開)脆弱性についても、挙動から推測するアルゴリズムが搭載されているソリューションもあり、リスクの兆候を早期に掴むことが可能です。
4つ目は「通知と対応の自動化」です。
リスクが検出された場合、即座にセキュリティチームにアラートを送信したり、チケットシステムと連携して対応を割り当てたりする機能も重要です。
加えて、既存のSIEM(Security Information and Event Management)やSOAR(Security Orchestration, Automation and Response)と連携することで、ASMの情報が全社的なセキュリティ運用に統合され、より効率的なインシデント対応が可能になります。
こうしたASMの機能は、単体で完結するものではなく、他のセキュリティソリューションと連携して初めて真価を発揮します。
たとえば、EDRやWAFと連携すれば、ASMで検出したリスクを即座に防御に反映することができますし、IT資産管理ツールと連携すれば、構成情報との照合によって“管理外資産”を特定することも可能です。
さらにASMは、導入初期だけでなく、常に監視を続ける「継続的管理」を前提としています。
IT環境は常に変化しており、新しいサービスの導入や設定変更によって、攻撃対象領域も日々変化しています。
この動的な変化を捉えるために、ASMは日次あるいはリアルタイムで資産を再スキャンし、変化点を検知する機能が求められるのです。
このように、ASMは単なる「チェックリスト」ではなく、企業のセキュリティ戦略を支える中核インフラの一部といえます。
資産の全体像を俯瞰し、リスクの優先順位を明確にし、タイムリーに対応するための基盤として、ASMは今後のセキュリティ設計に不可欠な存在になっていくでしょう。
実際に導入した企業が語る「見える化」の効果

アタックサーフェスマネジメント(ASM)を導入した企業の多くが、最初に実感する効果として挙げるのが「IT資産の見える化」です。
従来、IT資産の管理は情報システム部門の台帳や運用ツールに頼っていましたが、それだけでは把握しきれない“漏れ”が存在していました。
ASMの導入により、そうした認識外の資産まで可視化され、セキュリティリスクの真の全体像を把握できるようになったという声が非常に多く聞かれます。
たとえば、ある製造業の企業では、ASMを導入してすぐに、自社が把握していなかった複数のサブドメインや公開サーバーが存在していたことが判明しました。
それらは一部の部署が検証目的で立ち上げた環境だったものの、セキュリティパッチが未適用であり、結果的に外部からアクセス可能な“穴”になっていたのです。
もしASMを導入していなければ、それらは長期間にわたりリスクとして放置されていた可能性があります。
また、ITサービス企業の事例では、クラウド環境の変化に追従しきれずに古い設定が残っていたことが可視化されました。
具体的には、利用されなくなったAWSインスタンスが起動したままとなっており、アクセス制限がかかっていない状態で外部公開されていたのです。
ASMの継続的なモニタリングによって、このような“不要だが危険”なリソースの存在に気づくことができました。
さらに、ASMの「外部視点」での可視化は、経営層や非技術部門にも大きな影響を与えています。
多くの企業では、セキュリティリスクは抽象的で理解されにくいものとされがちですが、ASMのダッシュボードで「このように見られている」「これが狙われやすい」といった視覚的なデータを提示することで、経営判断の材料として有効に活用されているのです。
このことは、セキュリティ投資に対する社内の理解や合意形成にも寄与しています。
ASMによって可視化された脆弱性の存在は、単なる「警告」ではなく、「数値化されたリスク」として扱われ、CISOや経営層に対して具体的な説明責任を果たすことが可能になります。
これは、従来のセキュリティ対策にはなかった明確な成果指標を提供している点で、大きなメリットといえるでしょう。
加えて、グローバル展開している企業にとって、ASMの効果はさらに大きくなります。
国や地域ごとに展開しているIT拠点やクラウド環境に対して、統一的なポリシーと監視体制を敷くのは困難ですが、ASMを用いることで、全世界に広がる資産群を一元的に把握することが可能となります。
実際に、ある大手物流会社では、欧州拠点で使用されていたサードパーティ製サービスが原因で不正アクセスを受けていたことがASMによって判明し、即座に対処された事例があります。
このように、ASMによって得られる「見える化」は、単なる棚卸しにとどまらず、組織全体のセキュリティ認識を変え、対応力を根本から高める効果を持っています。
IT部門だけでなく、経営、現場、海外拠点までを巻き込んだセキュリティ対策の第一歩として、ASMの役割は極めて重要なものになってきているといえるでしょう。
セキュリティ強化だけじゃないASM導入の副次的メリット
アタックサーフェスマネジメント(ASM)は、その名称から「セキュリティ分野におけるリスク管理ツール」という印象を強く持たれがちですが、実際にはセキュリティ強化にとどまらない多くの副次的メリットをもたらします。
導入企業の事例を深掘りしてみると、「経営効率」「IT統制」「監査対応」「人材教育」など、組織全体の成熟度を押し上げる効果が随所に見られます。
第一の副次的メリットは、「IT資産管理の高度化」です。
多くの企業では、IT資産の管理がExcelや個別システムに依存しており、現実との乖離が起きがちです。
ASMを導入することで、これまで人手で行っていた資産棚卸し作業が自動化され、しかも“外部から見える”というセキュリティ視点が加わることで、正確かつ実践的な資産管理が可能になります。
このような可視化と自動更新によって、IT資産の統制レベルが一段と高まるのです。
第二に挙げられるのが、「監査対応の円滑化」です。
近年、金融業界や製造業を中心に、第三者によるセキュリティ監査やISMS認証、SOC2などの取得が重視されています。
ASMは、可視化された攻撃対象領域の記録やスキャン履歴をレポート形式で出力できるため、監査時のエビデンスとして活用できます。
実際、ある大手サービス業では、ASMで得られた脆弱性対応履歴とアラート履歴をそのまま監査資料として提示し、監査対応の負荷を大きく削減できたという事例もあります。
第三の効果は、「意思決定スピードの向上」です。
ASMは単なるリスクの洗い出しではなく、リスクの優先度や影響範囲をスコア化して提示するため、セキュリティチームがどこから対処すべきかを迅速に判断できます。
さらに、ダッシュボード化された視覚的な情報により、非エンジニア層であるマネジメント層や役員との会話もスムーズになり、リソース配分や外部委託の判断も迅速に行えるようになります。
第四に見逃せないのが、「社内教育・意識向上への寄与」です。
ASMによって、どの資産が脆弱で、なぜそれが問題なのかが明確になることで、技術部門以外の従業員も「どのような行動がリスクを生むか」を理解しやすくなります。
たとえば、外部公開のクラウドストレージの扱い、アカウントの共有設定、パスワードの管理方法など、具体的な事例を用いた社内研修にも応用できるため、全社的なセキュリティリテラシーの向上が期待されます。
さらに、間接的な効果として「ベンダーマネジメントの透明化」も挙げられます。
アウトソーシング先が構築・管理しているインフラに対しても、ASMは一貫してモニタリングを行います。
そのため、委託先に依存したブラックボックスな構成が可視化され、ベンダーとの契約見直しや、品質管理の根拠としても活用されることがあります。
これにより、企業はより透明性の高いITガバナンスを実現できます。
最後に、ASMの継続的な運用は「サイバー保険の契約条件の改善」にも寄与する場合があります。
一部の保険会社では、ASMやEDRの導入状況を保険料の評価基準に含めており、適切な可視化と管理体制が整っている企業は、より有利な条件で契約ができるケースも出てきています。
このような“金融的メリット”は、経営層にとって強力な説得材料になるでしょう。
このように、ASMは単なるセキュリティツールではなく、経営・運用・教育・保険といった多方面に価値を波及させる“全社的な資産”ともいえる存在です。
導入のきっかけはセキュリティ強化であっても、得られる効果は組織の多層的な変革へとつながっていくことが期待されます。
導入に伴う課題とそれを乗り越えた工夫

アタックサーフェスマネジメント(ASM)は多くのメリットをもたらす一方で、導入過程にはさまざまな課題が伴います。
特に、セキュリティツールとしては比較的新しいカテゴリであるため、社内理解の不足や運用設計の未成熟さが障壁となることもあります。
しかし、多くの先行導入企業はこれらの壁を乗り越え、独自の工夫でASMを定着させてきました。
まず大きな課題となるのが、「ASMの必要性に対する社内理解の不足」です。
ASMは“何かを守る”というより、“何が見えてしまっているかを明らかにする”アプローチのため、従来型のセキュリティ概念に慣れた現場ではその意義が理解されにくい傾向があります。
また、可視化された結果に対して「知らなかったから仕方ない」「過去に問題がなかった」といった反応が返ってくるケースもあり、初期フェーズでは担当部門間の温度差が課題になりがちです。
この点において有効だったのが、「経営層の巻き込み」と「具体的なリスク提示」です。
たとえば、ASMツールのダッシュボードで実際の脆弱性や公開資産の状況を視覚的に示し、万が一それが悪用された場合の影響とコストを数値化して提示した企業では、経営層の理解が飛躍的に高まりました。
これにより予算確保や運用工数の確保がスムーズになり、全社的な導入体制が整っていったという好事例もあります。
次に、「ASM運用体制の整備」も課題となります。
ASMは一度スキャンして終わるものではなく、継続的にモニタリングし、発見されたリスクに対して優先度を付けて対応していく必要があります。
しかし、既存のセキュリティチームにASM対応の工数を追加するのは現実的に難しい場合も多く、専任体制を組めないことが導入障壁になっていました。
ここで活用されたのが、「外部ベンダーの活用」と「他ツールとの連携」です。
たとえば、一部の企業では、ASMベンダーが提供するマネージドサービス(MSS)を利用し、運用の大半を外注しています。
また、SIEMやEDR、IT資産管理ツールと連携させることで、アラートの自動分類や対応フローの自動化を実現し、限られた人員でも十分なカバーができるよう工夫が施されていました。
さらに、「既存の業務フローとの整合性」も無視できない要素です。
ASMで発見されたリスクに対して、社内のどの部門が、どのように責任を持つかが明確になっていないと、対応が遅れたり、無視されるリスクも生じます。
このような事態を防ぐために有効だったのが、「事前の責任範囲の定義」と「インシデント対応マニュアルへの組み込み」です。
実際に、ASMにより発見された資産が、インフラチーム、開発部門、営業部門のいずれに属するのかを事前にマッピングしておくことで、対応の初動を迅速化した企業もあります。
加えて、「ASMの成果が定量化しづらい」という課題もあります。
見える化された脆弱性の数やアラート数は指標になり得ますが、これがどの程度リスク低減につながったのかを明確に示すのは難しい部分です。
この点においては、Before/Afterの資産総数やリスクスコアの変化を定期的に報告資料にまとめるなど、KPIベースの運用管理を工夫している例が見られました。
また、最も見落とされがちなのが「社内文化との整合性」です。
ASMは、攻撃者視点での情報を社内に突きつけるため、一部の担当者にとっては「指摘されている」と感じることもあります。
このような抵抗感を減らすために、「ASMは責任追及ではなく、組織全体の強化を目的としたもの」と繰り返し周知する姿勢が求められます。
教育研修や定例会での情報共有を通じて、ASMを“味方”として受け入れてもらう文化形成が成功の鍵を握るのです。
このように、ASMの導入には多面的な課題がありますが、適切な巻き込み、仕組み化、文化づくりによって確実に乗り越えることが可能です。
むしろ、これらのプロセスを経てこそ、ASMは組織に根づき、真に機能するセキュリティ基盤となっていくでしょう。
まとめ:ASMが企業にもたらす本質的な価値とは

アタックサーフェスマネジメント(ASM)の導入は、単なるセキュリティ対策の一環ではありません。
それは、現代の複雑化・分散化したIT環境における「新しい可視化のアプローチ」であり、企業のデジタル資産全体を“外部からどう見られているか”という視点で再構築する重要な戦略といえるでしょう。
この「見られている」という前提に立つことで、従来の防御姿勢を抜本的に見直すきっかけが生まれます。
まず第一に、ASMは企業の“見落とし”を洗い出す機能に優れています。
既存の資産管理だけでは把握しきれなかったクラウド上の一時リソース、過去の検証環境、外部公開設定のミスといった“管理外”の存在を自動的に検出し、それを攻撃対象領域として可視化することで、これまで想定されていなかったリスクを事前に封じ込めることができます。
これは防御の精度を一段階引き上げる、極めて実用的な効果といえるでしょう。
また、ASMは組織横断的な連携を促すツールでもあります。
セキュリティ部門だけでなく、開発、運用、経営層、さらには外部委託先までも含めた「全社的なセキュリティ統治」の起点となり、役割と責任の明確化、対策の優先順位設定、レポートの定期化といった継続的なプロセスの土台を提供します。
ASMという共通言語があることで、部門間の温度差や誤解が解消され、セキュリティが組織文化として根付いていくのです。
さらに、ASMは定量的なセキュリティ評価を可能にする点でも価値があります。
脆弱性の数、リスクスコア、攻撃可能性の推定などを数値化することで、従来は感覚に頼っていた判断が、データドリブンな意思決定へと変わります。
これは、限られた予算と人材をどこに集中すべきかを明確にするうえで、非常に重要な要素です。
“見える化”とは単なる可視性ではなく、“行動に移すための指針”として作用するのです。
加えて、副次的な効果も無視できません。
IT資産管理の正確性向上、監査対応の効率化、保険料評価への影響、社内教育への活用など、ASMはセキュリティ分野を超えて経営や運用の最適化にも寄与しています。
これは、導入当初は予想されなかった恩恵であり、「ASMの導入で会社の見え方が変わった」と語る企業も少なくありません。
もちろん、ASMの導入・運用には一定のハードルがあります。
社内理解の醸成、初期設定の整備、組織内の責任範囲の調整、成果の可視化といった課題を一つずつ乗り越える必要がありますが、それらを超えて得られるメリットは、十分に投資に見合うものです。
むしろ、これらのプロセスを経ること自体が、組織のセキュリティ成熟度を高めるトリガーになるといえるでしょう。
今後、ゼロトラスト、SOAR、EDR、SIEMなどと並んで、ASMは“次世代の基本装備”としての位置づけをより強めていくはずです。
インシデントが発生してから対応するのではなく、“発生するかもしれないリスク”を未然に可視化し、管理下に置く。
この能動的な防御姿勢こそ、現代のサイバー攻撃環境における最適解といえるのではないでしょうか。
アタックサーフェスマネジメントは、技術的なソリューションであると同時に、組織の行動を変える「仕組み」として機能します。
セキュリティの新たなスタンダードとして、今こそ積極的な導入と活用を検討する価値があるといえるでしょう。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。