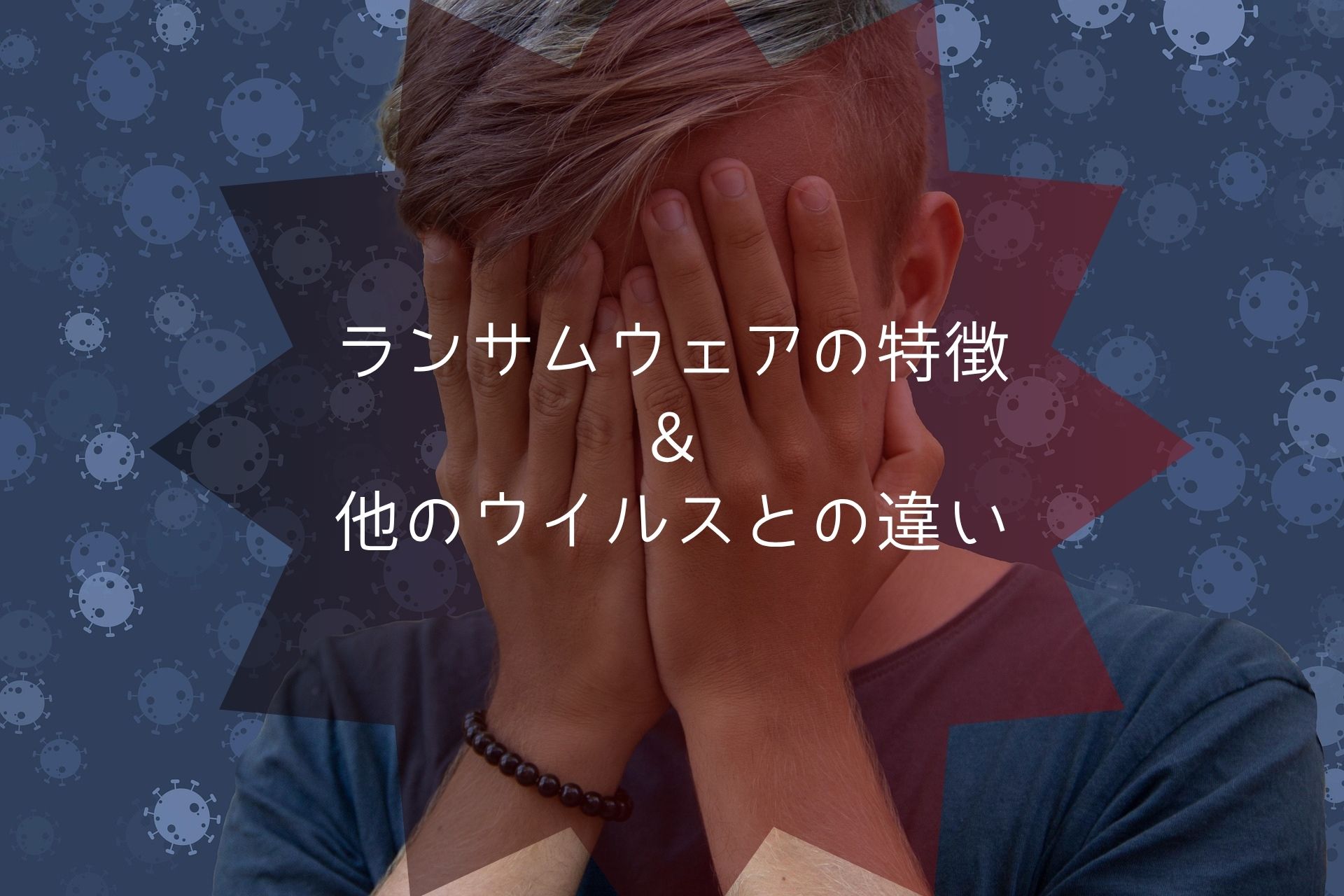近年、「ランサムウェア」というウイルスの名前を耳にする機会が急増しています。
これは単なるパソコンの不具合ではなく、ファイルが開けなくなり、復元のために金銭を要求されるという、極めて現実的で深刻なサイバー犯罪です。
この脅威は、企業の業務停止、個人の写真や資料の消失、さらには社会インフラへの影響にまで波及しています。
一方で、「コンピューターウイルス」とひとくくりにされがちな中で、ランサムウェアが他のウイルスとどう違うのか、正しく理解できている方は意外と多くありません。
本記事では、ランサムウェアの特徴と他のウイルスとの違いをわかりやすく比較しながら、被害事例や感染の兆候、そして今すぐできる実践的な対策について詳しく解説いたします。
なぜランサムウェアというウイルスが注目されるのか

ランサムウェアは、サイバー攻撃の中でも極めて注目度の高いウイルスです。
その理由は単純明快で、他の多くのウイルスと異なり、明確に「金銭」を目的とした直接的な脅迫行為を行うからです。
これまでのマルウェアの多くは、ファイルの破壊や動作の妨害、あるいは情報の抜き取りといった形で、利用者の不利益を目指すものでした。
しかしランサムウェアは、それらを超えて「金を払わなければデータを返さない」という、人質交渉のような性質を持ち、あからさまに損害を可視化してくるのです。
この性質が注目される理由には、被害の即時性と深刻さがあります。
感染した端末のファイルが一斉に暗号化され、復号のためには指定された額の暗号資産を支払うよう求められるという構図は、たとえば業務中に突然業務資料が全滅する、という状況を生み出します。
企業や自治体であれば、その日のうちに業務が全面停止し、病院であれば診療記録が開けず命に関わることもあり得ます。
この即効性のある混乱が、社会的な注目を集める最大の要因と言えるでしょう。
また、ランサムウェアは「RaaS(Ransomware as a Service)」という形で提供されるケースも増えています。
これは攻撃者が自身でウイルスを開発するのではなく、既存のランサムウェアキットをサービスとして購入・利用し、攻撃の成功報酬を開発者に分配する仕組みです。
これにより、プログラミングスキルのない攻撃者でも、高度なサイバー攻撃を仕掛けることが可能となり、被害の拡大に拍車がかかっています。
さらに近年では、「二重脅迫」「三重脅迫」といった高度な手法が登場しています。
二重脅迫とは、暗号化だけでなく機密データの窃取も行い、「復号しないだけでなく、このままでは情報を外部に公開する」と追加で脅す手法です。
三重脅迫に至っては、「取引先にデータ流出を知らせる」「顧客にも通知する」といった外部拡散も加え、被害者の社会的信用を強く揺さぶってきます。
これらの手口は、もはや単なるウイルス被害ではなく、組織の信頼・ブランド・法的リスクに直結する脅威としての重みを持っています。
ランサムウェアが注目されるもう一つの理由は、「被害が表面化しにくい」ことにもあります。
感染しても、企業側がその事実を公表することは稀です。
その理由は、株価下落や顧客離れを恐れる風評リスク、法的責任の拡大、内部統制の信頼喪失といった二次被害を避けるためです。
そのため、実際の被害件数は公表されているよりもはるかに多く、氷山の一角しか見えていないと専門家は指摘します。
また、インターネットを介して世界中どこからでも攻撃可能であることも、ランサムウェアの強みのひとつです。
言い換えれば、日本に拠点を持つ企業や個人も、世界のどこかにいる攻撃者の対象になる可能性が常に存在するのです。
攻撃側は特定の業種を狙う傾向もあり、たとえば医療機関、教育機関、中小企業など、IT対策が手薄になりやすい組織が集中的に標的にされています。
これは、支払う可能性が高い、バックアップ体制が弱い、法令対応が不十分など、攻撃側にとって「効率の良い相手」だからに他なりません。
加えて、テレワークの普及に伴い、セキュリティが整っていない個人端末や家庭用Wi-Fiルーターを経由した攻撃も増えています。
VPNの設定ミスや、RDP(リモートデスクトップ)機能の放置など、隙のある構成が攻撃の呼び水となり、そこから社内ネットワークへの侵入が始まるのです。
このように、ランサムウェアは単なるコンピューターウイルスの範疇を超えて、「組織運営そのもの」に直結する脅威となっています。
データを守ることは、もはやIT部門の責任ではなく、経営判断の一部である――そうした視点の転換が、ランサムウェア対策において今最も求められているものだと言えるでしょう。
ランサムウェアの特徴を他のウイルスと比較する

ランサムウェアは、同じ「ウイルス」と呼ばれるコンピュータマルウェアの中でも、特に目的が明確で、行動パターンが異なる点で特異な存在です。
その違いを明確にするには、まず従来のウイルスの特徴を確認し、それと照らし合わせながらランサムウェアの構造や振る舞いを理解することが重要です。
従来のウイルスは、主に感染・破壊・増殖を目的としたソフトウェアでした。
感染するとシステムの動作に異常をもたらし、特定のファイルを破壊したり、システムの起動を妨げたり、ウイルス自身を複製して他のファイルやデバイスに広がっていくといった特性がありました。
また、多くのウイルスはその存在を隠す「ステルス性」を重視しており、利用者が被害に気づかぬうちに動作を続けるタイプも少なくありません。
このため、検知されにくく、セキュリティ対策ソフトや専門家によるスキャンが必要になるケースが多々ありました。
これに対して、ランサムウェアはあえて「目立つ」存在です。
感染後はすぐにユーザーの目に付くような形で動作を開始し、デスクトップ画面に脅迫文を表示したり、ファイル拡張子を「.locked」や「.encrypted」などに変更することで、明らかに異常事態であると認識させます。
これは、ユーザーに「身代金を払わなければ復旧できない」という現実を突きつけ、心理的なプレッシャーをかけることで目的である金銭の支払いを促すためです。
従来型のウイルスが“隠れる”のに対し、ランサムウェアは“見せつける”という真逆のアプローチを取ります。
また、従来のウイルスは、ある種の“無差別攻撃”を行う傾向がありました。
広くネットワークを介してばらまかれ、個人・企業問わず不特定多数に感染する設計でした。
一方でランサムウェアは、しばしば「標的型攻撃」を伴います。
特定の業種や企業を狙い撃ちし、その組織構造やセキュリティ体制、業務上の重要ファイルの有無を事前に調査したうえで、感染を試みるのです。
これは、支払い能力やリスク感度を考慮して攻撃対象を選別する「犯罪としての効率化」が進んでいる証でもあります。
さらに、技術面でも大きな差異があります。
ランサムウェアは、ファイルの暗号化に強固な暗号技術(AESやRSAなど)を採用しており、一度鍵を失えば復旧はほぼ不可能です。
従来のウイルスによって破壊されたファイルは、システム復旧ツールである程度回復できる場合もありましたが、ランサムウェアの暗号化されたデータは事実上「封印」されるため、バックアップがなければ再取得は絶望的です。
もう一点の違いは、「交渉」が介在する点です。
従来のウイルスには、攻撃者と被害者の間に直接のやり取りは基本的に存在しませんでした。
ところがランサムウェアの場合、攻撃者が専用チャットを設け、交渉の場を設けるケースが非常に多くなっています。
支払額の交渉、期限延長の相談、復号の一部お試しなどがやり取りされ、まさに“人質事件”のような性格を帯びています。
これは、もはや単なるウイルスというより「犯罪サービス」の領域に踏み込んでいることを示しています。
また、スパイウェアやアドウェアといった他のマルウェアとも比較してみましょう。
スパイウェアは主にユーザーの行動や入力情報を監視し、第三者に送信することが目的です。
アドウェアは広告表示を通じて収益を得るために仕込まれます。
いずれもユーザーに気づかれず長期間にわたって活動することが前提ですが、ランサムウェアは短期決戦型です。
侵入後数分〜数時間でファイルを暗号化し、即座に金銭を要求するという性質上、「スピードとインパクト」を重視して設計されています。
このように、ランサムウェアは他のウイルスと比べて、「目的の明確さ」「感染後のアクション」「心理的圧力」「復旧困難性」「対人交渉の存在」といった点で、根本的に異なるマルウェアです。
これを正しく理解しない限り、一般的なウイルス対策だけでは対応しきれません。
ランサムウェアは、もはやウイルスの一カテゴリではなく、“戦術的サイバー犯罪”として独立して考える必要があるのです。
実際にランサムウェアに感染した事例とその原因
ランサムウェアというウイルスの脅威を正しく理解するには、実際の被害事例を知ることが最も有効です。
単なる技術的な問題としてではなく、組織や社会にどのような影響を与えたのか、なぜそのような感染が起きたのかを具体的に見ることで、現実味を持った対策につなげることができます。
ここでは、日本国内外で報告された代表的な事例と、その感染原因について解説いたします。
まず最初に紹介するのは、2021年に米国で発生したコロニアル・パイプライン社の事例です。
この企業はアメリカ南東部に燃料を供給する大規模なパイプラインインフラを管理していました。
攻撃を受けた結果、業務システムが停止し、石油供給が数日間ストップ。
全米でガソリンの買い占めが起こるなど、社会インフラに大きな混乱を引き起こしました。
原因は、VPN経由での不正アクセスであり、認証情報の漏洩がきっかけだったとされています。
攻撃者グループ「DarkSide」は、ランサムウェアを使って約75BTC(当時約5億円相当)を要求し、同社は実際に支払いを行いました。
次に、日本国内の有名な事例として、**名古屋港運営会社のシステム停止(2022年)**があります。
このケースでは、港のターミナル運営システムがランサムウェアによりロックされ、2日間にわたって輸出入の貨物処理が完全にストップしました。
原因は、運営会社が使用していた古いWindowsシステムの一部にパッチが適用されておらず、脆弱性が悪用されたことでした。
このように、物理的物流にまで波及する被害は「サイバー攻撃=デジタル空間の話」という常識を覆すものとなっています。
また、教育機関も被害が増加しているセクターの一つです。
ある国立大学では、職員のメールアカウントがフィッシングにより乗っ取られ、そのメールから複数の部署へランサムウェア付きの添付ファイルが送信されました。
結果的に、学内ネットワーク全体が遮断され、オンライン授業が停止。
学生のレポートデータも一部が失われるという事態に発展しました。
攻撃の背景には「セキュリティ教育の不足」「メールフィルタの誤設定」「多要素認証の未導入」など、複数の初歩的なミスが重なっていたことがわかっています。
中小企業も例外ではありません。
特に製造業や医療業界など、古い機器やソフトウェアを継続使用している業界では、サポートが終了しているシステムが狙われやすい傾向にあります。
ある中小製造業では、社内に設置されたNAS(ネットワーク接続ストレージ)を通じて感染が拡大しました。
このNASは、外部からのアクセスを許可したまま、初期パスワードすら変更されておらず、侵入口となったのです。
NAS内の設計図、顧客データ、製品仕様書などがすべて暗号化され、納期遅延や取引停止などの影響が長期にわたって残りました。
このように、感染の原因は一様ではありませんが、以下のような共通点が見られます。
- セキュリティアップデートの未適用
- VPNやRDPへの脆弱なアクセス制御
- メールフィルタやウイルス対策ソフトの誤設定
- 初期パスワードの使いまわしや放置
- 社員・職員へのセキュリティ教育の欠如
いずれも「基本的な対策」で防げた可能性が高いにもかかわらず、忙しさやコスト、技術的理解不足から後回しにされてきた項目ばかりです。
また、攻撃者が「確実に支払ってくれそうな相手」を狙っている点も見逃せません。
医療機関、地方自治体、中小企業など、業務が止まれば致命的になりかねない組織は、支払いの可能性が高いためターゲットにされやすいのです。
さらに、感染の「検知から報告までに時間がかかる」ことも多く、組織内での情報共有が不十分であれば、被害は短時間で全体に波及します。
これらの事例から明らかなのは、「特別な企業が狙われる」のではなく、「守りが弱いところから順に狙われている」という事実です。
ランサムウェアはランダムではなく、戦略的に設計された攻撃です。
だからこそ、同様の被害を避けるためには、事例から学び、弱点を客観的に見直す視点が必要不可欠なのです。
感染したときに見られるランサムウェア特有の兆候

ランサムウェアは、その性質上、感染直後に非常にわかりやすい“異変”を伴います。
これは、攻撃者が金銭を要求するビジネスモデルを採っているため、「被害者が異常に気づかなければ意味がない」構造になっているからです。
したがって、早期発見ができれば被害の拡大を抑えることが可能であり、兆候を見逃さないための知識が重要になります。
ここでは、ランサムウェア感染時に見られる典型的な兆候とその裏側の技術的挙動について解説します。
まず、最も明確で頻出する兆候がファイルの拡張子変更です。
通常であれば「.docx」や「.jpg」「.xlsx」といった一般的な拡張子が、「.locked」「.crypt」「.encrypted」など見慣れない形式に一斉に変わっている場合、これはランサムウェアによる暗号化の証拠です。
ファイルを開こうとしてもエラーが表示され、ソフトウェアでは開くことができません。
また、ファイルアイコンの表示も無効化されていることが多く、視覚的にも異常に気づくよう設計されています。
次に挙げられるのは、脅迫文(ランサムノート)の出現です。
デスクトップやファイルフォルダ内に「README.txt」「DECRYPT_INSTRUCTIONS.html」「RECOVER_FILES」といった名称のファイルが突然現れ、その中に暗号資産での支払い方法や復号キーの取得手順が記されています。
また、脅迫文が壁紙として設定され、パソコン起動時に大きく表示されることもあります。
そこには「〇〇時間以内に支払わなければファイルは消去される」「交渉にはこのチャットサイトを使え」といった、極めて現実味のある言葉が並びます。
感染後は、パソコンやサーバーの動作が著しく重くなるという症状も発生します。
これは、内部で数千〜数万単位のファイルを一気に暗号化するプロセスが走っているためです。
CPUやディスクI/O、メモリ使用率が急上昇し、処理速度が著しく低下します。
多くのランサムウェアは、ファイル暗号化と同時にバックグラウンドでセキュリティソフトの無効化やログの消去も行っているため、動作の遅さとセキュリティ機能の停止が同時に進行するのが特徴です。
加えて、セキュリティソフトの挙動異常や強制終了も重要なサインです。
突然アンチウイルスが停止していたり、リアルタイム保護がオフになっていたりする場合、すでに感染が進行している可能性があります。
特にエンドユーザーが設定を変更していないにもかかわらず保護状態が無効になっている場合は、内部で悪意あるプログラムがシステム制御を奪っているサインです。
さらに、ネットワークを介しての急速な感染拡大も特徴的です。
一台が感染すると、社内ネットワークを通じてNASや共有フォルダ、他のPCに自動的に感染が広がっていくことがあります。
特に、管理者権限を持った端末が最初に感染した場合、その権限を利用してドメイン全体に暗号化指令が走るケースも報告されています。
このような連鎖を防ぐには、最初の感染端末を即座にネットワークから切り離すことが極めて重要です。
通信ログやファイアウォールの挙動変化も見逃せません。
外部との不審な通信(特にTorネットワークや特定のIPアドレスへの接続)が検出される場合、それは攻撃者との通信チャネルが形成されている証拠かもしれません。
企業であれば、SIEMやEDRのログを分析し、通常とは異なるデータ送信やプロセス実行が確認された時点で即座に対応を開始すべきです。
また、感染からすぐに被害が発生するとは限らないことも理解しておくべきです。
最近の高度なランサムウェアは、あえて即時に暗号化を行わず、数週間から数ヶ月にわたって内部ネットワークを探索し、最大の被害を与えられるタイミングで発動するものもあります。
この「潜伏型」のランサムウェアは、事前にバックアップ経路や共有ドライブを把握したうえで、それらを一斉に攻撃することで、復旧手段さえ奪い去ろうとするのです。
こうした兆候をいち早く察知し、感染端末のネットワーク遮断や調査の着手ができる体制があるかどうかが、被害を“兆候レベル”で食い止める鍵となります。
そのためには、**社内全体で「不審な挙動に即座に気づける目」と「報告をためらわない風土」**を育てることが、最も実効性の高い防御策と言えるでしょう。
ランサムウェア型ウイルスに有効な具体的対策方法
ランサムウェアというウイルスは、その被害の即時性と深刻さゆえに、「予防」「早期発見」「初動対応」の3段階すべてにおいて、戦略的な対策が求められます。
ただ単にアンチウイルスソフトを導入するだけでは不十分であり、組織全体の体制や日常業務の習慣、そして技術的な多層防御の構築が必要です。
ここでは、実効性の高い具体的対策を6つの視点から解説いたします。
1. メールセキュリティの強化と運用教育
ランサムウェア感染の最大の侵入口は「メール」です。
特に標的型メール攻撃(スピアフィッシング)は、取引先や同僚になりすました巧妙な文面で、添付ファイルや偽装リンクを開かせることによってマルウェアを実行させます。
このため、メールにおける危険の見極めを、単にシステムに頼るのではなく、人間の判断力を向上させる必要があります。
具体的には、以下のような教育を繰り返し実施することが有効です。
- 添付ファイル付きメールは開封前に送信元ドメインを確認する
- リンクにマウスを乗せて、遷移先URLを確認する
- 社内報告ルールを整備し、不審メールは全社に即共有する
あわせて、メールフィルタやスパム対策ソリューション(例:サンドボックス解析、DKIM/SPF/DMARC)を導入し、自動的にリスクを排除する技術的対策も強化すべきです。
2. 脆弱性管理とアップデート運用の徹底
OSやアプリケーションの脆弱性は、ランサムウェアが内部侵入するための“裏口”です。
実際、WannaCryやPetyaといった大規模感染事例の多くは、既知の脆弱性を放置していたことが主な原因でした。
対策としては以下のような仕組み化が求められます。
- Windows Updateやアプリの更新をスケジュール化する
- 脆弱性診断ツール(例:Qualys、Nessus)を定期運用する
- サポート切れシステムの運用停止または更新計画の明文化
アップデートを単なる「技術的作業」として捉えず、「経営リスクの軽減措置」として全社的に扱うことが重要です。
3. バックアップ戦略の最適化
「感染は防げなくても、被害は最小化できる」――これがバックアップの本質です。
ただし、単にデータを保存しておくだけでは意味がありません。
ランサムウェアは、同一ネットワーク内のバックアップ領域まで暗号化対象に含めるケースがあり、“隔離”された保存方法が不可欠です。
有効なバックアップ戦略のポイントは以下の通りです。
- 社内ネットワークと物理的・論理的に分離されたバックアップ環境を構築
- 1日単位、週単位など複数世代のスナップショットを保持
- バックアップ完了の成否確認を自動レポートで把握
- テスト復元を定期的に実施し、実際に使えることを確認
クラウドサービスを活用する場合も、バックアップ領域へのアクセス権限やAPI制御の厳格化が求められます。
4. エンドポイント防御と検知体制の導入
従来型のアンチウイルスソフトでは、日々進化するランサムウェアを検知しきれないケースが増えています。
そこで注目されているのがEDR(Endpoint Detection and Response)やNGAV(次世代アンチウイルス)です。
EDRは、以下のような防御+検知の機能を提供します。
- ファイル暗号化やレジストリ改変といった不審な動作をリアルタイム監視
- 感染端末を自動でネットワーク隔離
- 管理者へ即時通知し、ログ解析と初動対応を支援
これにより、「侵入されても即遮断・調査・除去」が可能となり、重大インシデントへの発展を防ぎます。
5. 権限管理とアクセス制御の強化
ランサムウェアは、感染端末が高い管理権限を持っていればいるほど、組織内での拡散力を高めます。
そのため、最低限の権限だけを各ユーザーに与える「最小権限の原則(PoLP)」を徹底することが求められます。
具体的には:
- 管理者権限アカウントと一般業務用アカウントを分離
- 共有フォルダのアクセス権限を必要最小限に制限
- 特定ユーザーや業務時間帯に限定したRDPアクセス許可設定
また、ログイン失敗回数の上限や多要素認証(MFA)の適用も、外部からの侵入リスクを大幅に低減させます。
6. インシデントレスポンス体制の整備
最後に、どれだけ対策を講じていても“ゼロリスク”は存在しません。
そのため、実際に感染したときの「初動対応力」が組織の命運を分けます。
最低限、以下のような手順書と訓練を準備すべきです。
- 感染時のネットワーク遮断フロー
- 通信ログやPCメモリの保全手順
- 管理者・経営層・広報へのエスカレーションライン
- 警察庁・サイバーセキュリティ専門会社との連携体制
- 被害報告や情報漏えい時の社外対応テンプレート(顧客通知・報道対応)
このように、ランサムウェアへの対策は「IT施策」ではなく、「全社的な防災活動」として捉える必要があります。
人・技術・運用のすべてがかみ合ったとき、はじめて“実効性のある防御”が成立するのです。
まとめ:ウイルスの中でもランサムウェアが最も警戒される理由とは
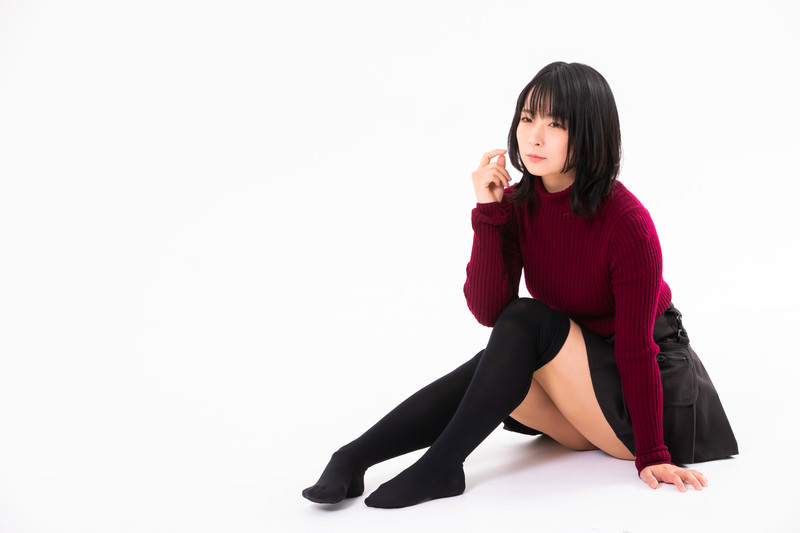
ランサムウェアは、数あるマルウェアの中でも際立った危険性を持つ存在です。
それは単なる「コンピューターウイルス」の一種ではなく、明確な金銭目的を伴い、攻撃者と被害者の“交渉”を前提とした犯罪モデルに基づいて設計されています。
感染すれば業務が即座に停止し、重要なファイルがアクセス不能になるだけでなく、復旧の可否すら攻撃者の手に委ねられるという圧倒的なコントロールの喪失が発生します。
このような特性が、ランサムウェアを他のウイルスよりも数段階上の脅威として位置づけている理由です。
また、ランサムウェアは単にデータを暗号化するだけでは終わりません。
近年では「二重脅迫」「三重脅迫」といった高度な攻撃が主流となり、機密情報の窃取と公開をちらつかせながら、被害者の信用や評判を人質に取るような圧力が加えられます。
この結果、感染者は「業務停止」「金銭被害」「信用喪失」「法的リスク」という四重苦に晒され、たとえ復旧に成功してもダメージが長期間にわたって残るのです。
さらに恐ろしいのは、ランサムウェアの“サービス化”が進んでいる点です。
RaaS(Ransomware as a Service)というビジネスモデルが登場し、誰でも簡単に攻撃ツールを利用できる時代が到来しています。
これにより、かつては高度な技術を持つ一部の攻撃者しか行えなかったランサムウェア攻撃が、広く一般化しつつあります。
攻撃者の数が増え、手口が多様化し、標的が拡大すれば、当然ながら被害の裾野も広がっていきます。
私たちは「ウイルス」と聞くと、昔のようなコンピューターの不調やイタズラ的な破壊行為を想像しがちです。
しかし、ランサムウェアはそのような認識では対応できない現実的な脅威です。
攻撃は巧妙で、目的は明確、手段は多様で、そして損害は甚大。
そのため、単なるIT部門の課題としてではなく、経営リスク、業務継続、情報資産の保全、さらには社会的責任として捉える必要があります。
ここまでの記事で、ランサムウェアの特徴、他のウイルスとの違い、典型的な感染事例、感染時の兆候、具体的な対策といった要素を体系的に整理してまいりました。
重要なのは、これらを「知識」としてとどめるのではなく、組織内の具体的な行動計画として実装することです。
たとえば、
- 毎月1回のアップデート確認を“業務として”実施しているか
- 社内に「不審メール報告ルール」があるか
- 社員に向けたセキュリティ研修が年に1回以上行われているか
- 管理者権限アカウントが実際に分離されているか
- バックアップデータの復旧テストが行われているか
こうした取り組みが積み重なった結果、初めて「感染しても復旧できる組織」が生まれるのです。
セキュリティ対策は完璧でなくて構いません。
しかし、「備えがある」という状態は、被害の深刻度を劇的に変えます。
ランサムウェアは、単なるIT課題にとどまらず、今や経営判断の質そのものが問われる時代に突入しています。
IT部門だけに任せるのではなく、経営者・人事・現場・全社員が“主体的にかかわるべきリスク”であるという認識を、組織全体で共有することが、最大の防御力となります。
最後に強調したいのは、ランサムウェアは「防げる」脅威であるということです。
被害事例の多くは、パッチ未適用、教育不足、初動の遅れといった基本的なミスから始まっています。
つまり、正しい知識と日常の備えさえあれば、感染を防ぎ、万が一のときにも組織を守ることができるのです。
ランサムウェアという現代型ウイルスに立ち向かう鍵は、“最新のツール”でも、“高価な製品”でもなく、日々の“基本行動の継続”にあります。
今この瞬間から、一歩ずつ、備えを始めましょう。
それが、すべてのウイルスよりも警戒すべきランサムウェアから、自分自身と大切な情報を守る最善の方法です。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。