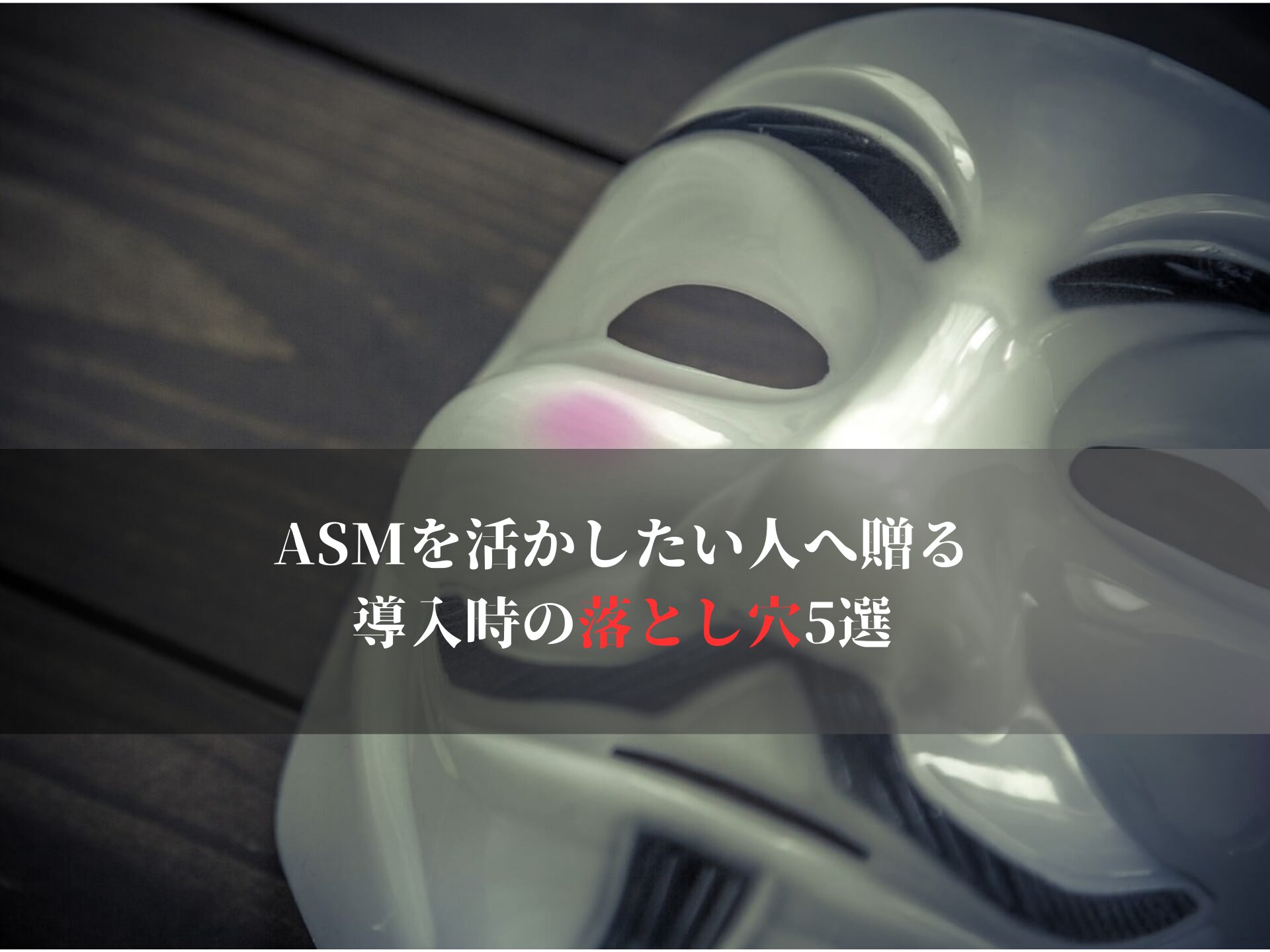ASM導入が注目される背景と企業の期待

近年、情報セキュリティの現場では「ASM(Attack Surface Management)」というキーワードが急速に存在感を増しています。
背景にあるのは、企業を取り巻くIT環境の変化と、それに伴うサイバーリスクの複雑化です。
これまでのような境界型防御では守りきれない“見えないリスク”が拡大し、可視化と管理の必要性が急速に高まっています。
特にクラウドサービスの普及、テレワークの一般化、サードパーティ連携の増加といった要因により、企業が管理すべきIT資産は物理的な社内ネットワークの外へと拡張されています。
このような環境では、「気づかぬうちに露出しているサーバーやAPI」「使われていないが公開状態のまま残っているドメイン」などが攻撃対象となり得ます。
この“攻撃対象領域”の管理を自動化・体系化する取り組みこそがASMです。
外部から見える資産をスキャンし、企業自身が把握しきれていないリスクを明るみに出す。
いわば「攻撃者視点で自社を可視化する」ための仕組みであり、従来の内部ログ監視やアンチウイルスとは異なる角度の防御ラインを築く役割を担っています。
こうした背景を踏まえ、国内外のセキュリティガイドラインにもASMの導入は推奨されつつあります。
たとえば、経済産業省が公開した「ASMガイダンス」では、企業のセキュリティ対応における“入口管理”の第一歩としてASMを導入すべきであるという考え方が明確に示されています。
今やASMは「やっておいたほうがいい対策」ではなく、「やらなければならない管理」となりつつあるのです。
さらに注目すべきは、ASMが単なるセキュリティ施策にとどまらず、企業のガバナンスや経営判断にも資する情報を提供できるという点です。
どの部門がどのような資産をどこで使っているのか。
どの資産が外部とどのような形で接続されているのか。
これらを可視化し、全社的な資産管理の基盤に据えることができれば、リスクマネジメントだけでなく、事業継続計画(BCP)や内部統制にも役立てることが可能です。
その一方で、ASM導入に対する現場の理解やノウハウはまだ成熟しておらず、導入直後に“想定外”の問題に直面する企業も少なくありません。
たとえば、「何をもってリスクと判断するのか」「どこまでの範囲をASMの対象にするのか」といった基本方針が曖昧なまま運用を始めてしまい、結果的にレポートだけが積み上がり、何もアクションにつながらないというパターンも見受けられます。
ASMは、単なるスキャンツールの導入ではありません。
組織的な対応、運用体制の設計、ガバナンスへの統合を含めた“全社的な管理プロジェクト”として捉える必要があります。
そのためにも、導入時点での期待値を適切に設定し、経営層・実務部門双方が共通認識を持って取り組むことが極めて重要だといえるでしょう。
見落とされがちなASM導入の誤解

ASM(Attack Surface Management)は、攻撃者視点で外部公開資産を洗い出すことで、企業のリスクを可視化する極めて有効な手段です。
しかし実際には、その本質を誤解したまま導入を進め、十分な効果が得られないケースが後を絶ちません。
ここでは、ASM導入時によく見られる誤解と、その背景にある認識のズレを明らかにしていきます。
まず最も多い誤解が、「ASMは脆弱性スキャンの延長線上にあるツールだ」という認識です。
確かに、ASMも外部からアクセス可能な資産に対してスキャンを行い、リスクを抽出するという点では共通しています。
しかしその目的は、既知の脆弱性の有無を確認することではなく、“攻撃対象になり得るすべての露出領域”を洗い出し、常時監視し続けることにあります。
スキャナではなく“監視基盤”として理解することが、正しい捉え方といえるでしょう。
もうひとつの誤解は、「ASMは導入すれば自動的に守ってくれる」という過信です。
これは多くのセキュリティ製品に共通する問題でもありますが、ASMは“警告を出すだけ”の仕組みであり、それをどう読み取り、誰が対応し、どのように改善するかは、組織の運用体制に委ねられています。
たとえば、ASMで“意図しない外部公開”が見つかったとしても、それを放置すれば何の意味もありません。
ASMの効果は、「運用プロセスに組み込まれてこそ」発揮されるのです。
さらに、対象範囲の誤解も多く見られます。
導入時に「公開中の本番環境だけ見ていれば十分だ」と考え、開発中の環境やテストサーバー、古いサブドメイン、クラウド上の不要なストレージなどを対象外としてしまう企業も存在します。
しかし、攻撃者は“本番か否か”など意に介しません。
「どこかに脆弱な入り口があるか」を探しているだけであり、運用されていない資産ほど監視が緩く、狙われやすいという現実があります。
加えて、「ASMの導入=初期スキャンで十分」と考えてしまうのも大きな誤解です。
ASMの価値は“継続的な監視と更新”にあります。
クラウド環境の設定変更、新規サービスの追加、契約終了済みの外注先による資産放置など、IT環境は日々変化します。
その変化に追従できなければ、ASMの情報はすぐに古くなり、リスクの兆候を見落とすことになります。
また、検出された情報の解釈にも注意が必要です。
「スコアが低い=安全」と早合点してしまい、本来対応が必要なアラートをスルーしてしまうことも。
ASMツールの出力結果はあくまで“指標”であり、実務上の重要度や業務影響を踏まえた分析と対応判断が不可欠です。
これらの誤解が放置されたままだと、ASMは「高価なレポート作成ツール」と化し、実際のリスク低減にはつながりません。
導入前には、ASMの目的、対象範囲、運用方法を関係者間で正しく共有し、運用フェーズの設計まで視野に入れる必要があります。
ASMとは、導入した瞬間から“継続的に学習し続けるプロセス”でもあります。
導入部門だけで完結させず、セキュリティ部門、インフラ管理部門、開発部門、経営層まで含めた“全社的な理解と体制”のもとで、誤解を解き、共通言語として浸透させていくことが、失敗回避の第一歩といえるでしょう。
体制未整備でつまずくASM運用初期フェーズ

ASM(Attack Surface Management)の導入には、技術的な準備と同じくらい、組織体制の整備が重要です。
多くの企業で見られるのは、「ツールの導入まではスムーズだったが、その後の活用が定着しなかった」という事例です。
この背景には、運用フェーズにおける役割分担の曖昧さや、関係部門間の連携不全があります。
まず典型的な問題は、「ASMを誰が運用するのかが決まっていない」ことです。
たとえば、情報システム部門がツール選定と導入を担当したものの、導入後に脆弱な資産が検出された際、その対処はセキュリティ部門なのか、インフラ担当なのか、はたまた業務部門なのかが不明確なまま放置されてしまう。
こうした“受け皿不在”の状態では、どれだけ優秀なツールであっても、リスクの早期対処にはつながりません。
さらに問題を複雑にしているのは、ASMが“横断的な管理領域”であることです。
たとえば、不要なDNSレコードやクラウド上の放置されたストレージは、開発部門の責任であったり、外注ベンダーが構築したものであったりと、単一の部署で完結しないリスクが多数存在します。
にもかかわらず、「導入は情シス部門の管轄だから」といった理由で、他部門との連携が疎かになるケースも少なくありません。
また、ASMの結果を活用するためには、対応フローの明文化と継続的なモニタリング体制の構築が不可欠です。
具体的には、検出内容の確認→影響範囲の分析→対策の実施→結果の反映というサイクルを回す仕組みが必要です。
この流れが整っていないと、レポートが一方的に出力されるだけで、対応は後回しにされ、気づけばリスクが放置されたまま──という事態を招きます。
たとえば、ある企業では、ASM導入から1ヶ月で30件以上の“要対応アラート”が検出されたにもかかわらず、誰も手をつけずに放置されていました。
理由は「誰がどこまで対処するか決まっていなかった」「優先度が不明だった」「経営層への報告ラインがなかった」など。
このような状況は、ASMの本来の価値を損なうだけでなく、むしろ“気づいたのに放置していた”という、法的・倫理的リスクにさえつながりかねません。
さらに、ASMを実務に根づかせるには、KPIの設計と組織内の共有も欠かせません。
たとえば、「検出アラートの対応完了までの平均時間」「放置アラート数の推移」「改善率」など、定量的な評価指標を設けることで、運用チームの成果が見える化され、改善のモチベーションにもつながります。
このKPIを経営層と共有し、定期的に報告する仕組みがあれば、ASMの運用は“技術者任せの施策”ではなく、“経営資源としての投資”へと昇華します。
また、外部ベンダーと連携している企業の場合、SLA(サービスレベルアグリーメント)へのASM結果の反映も検討すべきです。
たとえば、外注されたシステムの構築や保守がASMで検出されたリスクと結びついている場合、契約範囲として是正を求められるように明文化しておくことで、対応責任の明確化とスムーズな修正が可能になります。
ASMは単なるITツールではありません。
それは「組織の情報統制力を問うリトマス試験紙」といえる存在です。
導入段階で“体制設計”を怠れば、ASMは単なるレポート出力装置に成り下がります。
逆に、対応責任の明確化、フローの整備、関係部門との連携体制を整えることで、ASMは“能動的リスク制御の中核”として機能し始めるのです。
このフェーズを乗り越えられるかどうかが、ASM導入の明暗を分ける分岐点だといえるでしょう。
ツールに頼りすぎた結果、見落とされた脅威とは

ASM(Attack Surface Management)は、外部公開されたIT資産を継続的に監視し、リスクを可視化する極めて有効な手段です。
しかし、ここにひとつ大きな落とし穴があります。
それは、「ツールさえ入れれば、すべてを見つけてくれる」という過信です。
この誤信によって、実際には多くの企業が“検出されたはずの脅威を見落とし、放置し、結果として重大なインシデントに発展する”という事態を経験しています。
ASMツールは高精度なスキャン機能を備えており、数千ものIPアドレスやDNSレコード、クラウド資産を自動的に調査し、異常やリスクを通知してくれます。
しかし、ここで誤解してはならないのは、「ASMはあくまで“通知”するだけ」であって、「判断」や「対処」までは行わないということです。
たとえば、ある企業ではASMのダッシュボードに「公開中の古い開発サーバーが第三者からアクセス可能」という警告が3週間以上表示されていました。
にもかかわらず、誰もそのアラートを“危険”とは認識せず、結果としてそのサーバー経由で社内システムに侵入され、個人情報が流出しました。
原因は、ツールのアラートを「ただの情報」として放置したこと、つまり運用側の受け止め方の軽視です。
さらに問題なのは、ASMが検出できる情報にも限界があることです。
たとえば、内部からしかアクセスできないが設定ミスで外部接続可能になっているような資産は、外部スキャンでは発見が困難です。
また、Webアプリケーションの脆弱性やAPIの認証設定ミスなど、ツール単体では検出しきれない要素も多く存在します。
つまり、ASMは“万能の目”ではないという現実を理解しなければなりません。
また、ASMツールの出力結果は膨大な情報量を伴います。
数百〜数千件におよぶアラートや通知を前に、何が重要で、何が無視してよいのかの判断がつかず、結局すべてが“情報の海”に埋もれてしまうことも珍しくありません。
この状態を「アラート疲れ(alert fatigue)」と呼び、特に運用体制が脆弱な組織では深刻な課題となります。
この問題を避けるには、まずASMのアラートを仕分け・分類するルールを事前に整備しておくことが重要です。
「公開予定の資産か否か」「部門の所有者が明確か」「過去のリスク履歴との関連性があるか」など、複数の視点から優先順位をつける工夫が必要です。
さらに、ASMを単なる“セキュリティ部門のツール”とせず、資産管理・クラウド運用・開発部門などの横断的な情報基盤として捉えることも求められます。
たとえば、クラウド運用部門がASMのダッシュボードを定期的に確認し、タグ付けされていない資産を棚卸しに回す。
開発部門が新規サービスを公開する際には、ASMとの整合性チェックを事前工程に組み込む。
こうした仕組みがあることで、“発見されたが放置されたリスク”を減らすことができます。
また、ツールの検出範囲や精度は、導入時の設定や契約内容によって大きく異なります。
一部のASM製品ではクラウド特化型やIoT資産検出に強みを持つものもあれば、逆にオンプレミス系資産に弱いツールもあります。
そのため、自社のIT構成に合致したツール選定と、定期的な設定見直しが不可欠です。
最終的に重要なのは、「ASMを導入したから安全」ではなく、「ASMのアラートを人が解釈し、判断し、行動に移すこと」が運用の要であるという点です。
ASMは“人の目と判断力を拡張する道具”に過ぎず、放置すれば単なる静的レポートと化します。
ASMの本来の力を引き出すためには、技術と人、運用と教育、可視化とアクションを結びつける視点が欠かせないといえるでしょう。
ASM導入後も求められる継続的な見直しと改善

ASM(Attack Surface Management)は、導入した時点が“スタートライン”であり、そこからいかに運用・改善を続けていけるかが成果の分かれ目となります。
しかし、実際の現場では「導入まではうまくいったが、その後の活用が停滞している」という声が少なくありません。
これはASMに限らず、あらゆるセキュリティ施策に共通する課題ですが、ASMの場合は特に“継続性”が命となるのです。
ASMの最も重要な特性のひとつは、“企業のIT資産は常に変化している”という前提を前提とした動的な監視です。
クラウド上で新しいサービスが立ち上がったり、既存の資産が不要になって削除されたり、あるいは外注先が構築した環境がそのまま放置されたり──こうした日常の中で、攻撃対象領域は日々変わっていきます。
したがって、「一度すべてを棚卸ししたから終わり」ではなく、常に最新の資産状態を把握し続ける仕組みが求められます。
そのためにまず必要なのは、定期スキャンとその分析プロセスのルーティン化です。
たとえば、「週1回のフルスキャン」「月1回の変化差分レポートのレビュー」「四半期ごとの脆弱資産棚卸し」など、周期を明確にし、実行責任を持たせることが重要です。
これを実現するには、単なる“ツール導入”ではなく、“プロセス設計”が必須なのです。
次に重要となるのが、検出結果へのリアクション体制の整備です。
多くの現場で見られるのが、ASMが生成するアラートやレポートが「誰にも読まれずに蓄積されていく」状態です。
これを避けるためには、リスクのレベルに応じた対応フローの明確化が必要です。
たとえば「高リスク=即時対応」「中リスク=1週間以内に評価」「低リスク=次回レビュー対象」といった形で、アラートを分類し、それぞれの対応スケジュールをルール化します。
また、改善結果を記録し、次回のスキャンで確認するというフィードバックループを構築することで、運用の質は大きく向上します。
そして、ASMの運用改善を加速させるために有効なのが、KPIの導入と可視化です。
たとえば、「脆弱資産の検出数」「リスク対応までの平均時間」「前月比のリスク削減率」といった定量指標を定め、社内で定期的に共有することで、組織全体の意識が変わります。
これにより、「ASMをなぜ続けるのか」という問いに対する納得感と正当性が生まれ、継続的な投資と支援を得やすくなります。
また、改善の文脈で見落とされがちなのが、“ASM導入直後に定義したポリシーやスコープが現在の実態と合わなくなっている”という点です。
たとえば、当初はオンプレミス中心の環境を前提にしていたが、2年後にはクラウド移行が進み、対象資産や脅威の種類が大きく変化している──という状況は珍しくありません。
このようなケースでは、ASMの対象スコープそのものを見直す必要があります。
また、スキャン設定や対象ドメイン、検出項目なども定期的にチューニングを行い、現状に即した設計へアップデートしていくことが求められます。
さらに、外部の支援を活用することも選択肢のひとつです。
専門ベンダーによる運用支援や定期レビュー、改善提案などを受けることで、自社だけでは気づけない盲点を補完し、より高度なASM活用が可能になります。
とくに中堅〜大企業では、セキュリティ体制の内製化が難しい場合があるため、マネージドASMサービスを活用することで安定した運用を実現している企業も増えています。
継続的な改善という観点で重要なのは、ASMを“ツール”ではなく“文化”として根づかせることです。
すなわち、「何か問題が起きたときに確認する道具」ではなく、「普段から意識の中にある、日常のセキュリティ監視インフラ」として浸透させることが、最も理想的なあり方です。
ASMは、放置すれば“静的なレポート”で終わります。
しかし、運用の仕組みを整え、継続的に見直し、組織全体で活用する文化があれば、それは“動的なリスク制御の中枢”として機能します。
この運用フェーズこそが、ASMの真価を発揮する場所なのです。
まとめ:ASMを成功に導くために避けたい5つの落とし穴
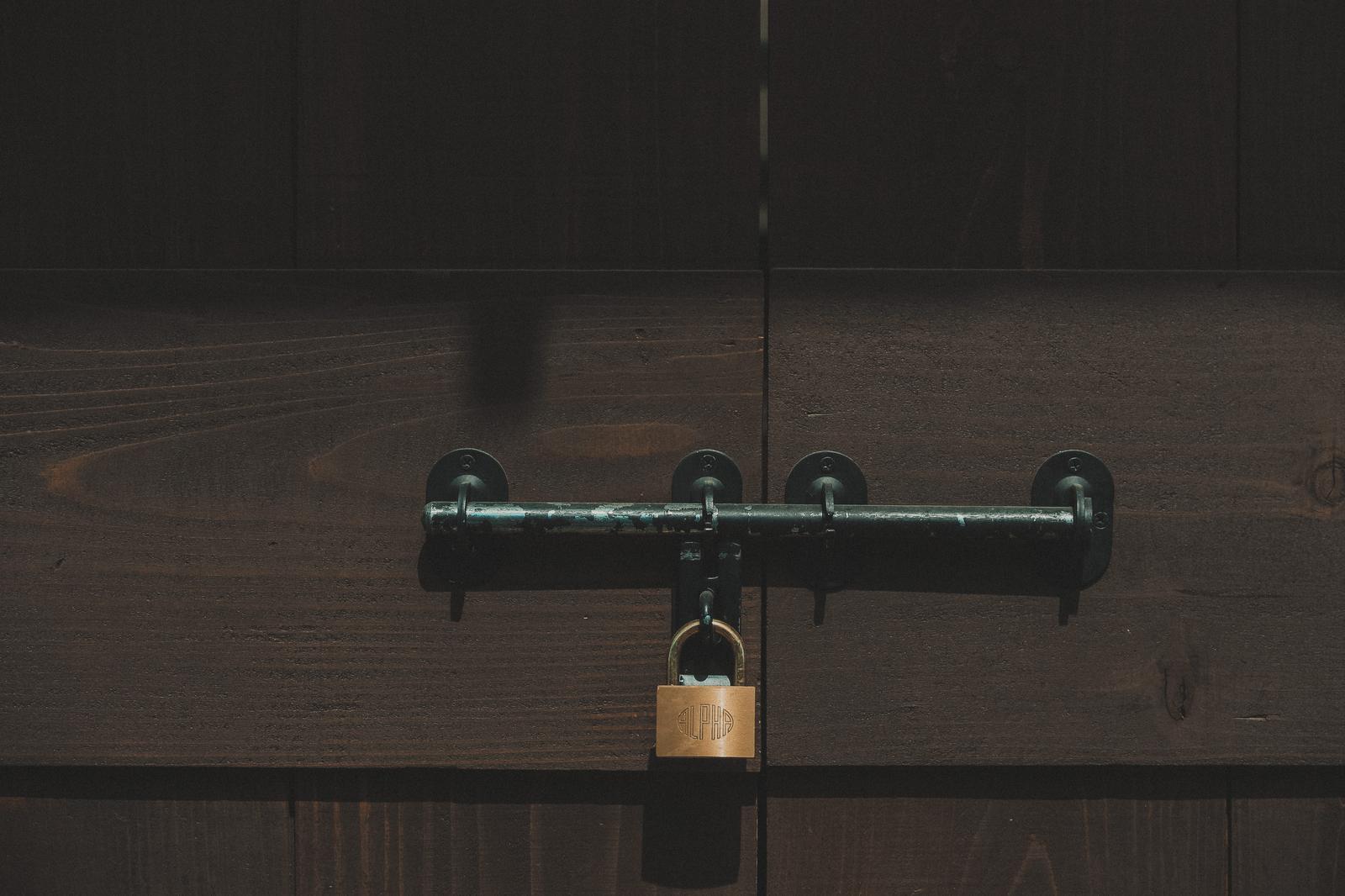
ASM(Attack Surface Management)は、サイバー攻撃の入り口となる「外部公開資産」を可視化・管理し、リスクを能動的に制御するための極めて重要な手法です。
クラウドの普及やリモートワークの浸透により、企業のIT資産は複雑化し、従来の防御では守りきれない時代に突入しました。
こうした中で、ASMは単なる技術導入ではなく、「企業のセキュリティ意識を再構築する機会」としても注目されています。
しかしながら、ASMを導入した多くの企業が、“期待した効果が得られなかった”という現実に直面しています。
その原因の多くは、技術的な問題ではなく、“組織的・運用的な落とし穴”に陥っている点にあります。
本記事では、そうした失敗につながる典型的な落とし穴を以下の5つに整理しました。
1. ASM導入の目的や役割を誤解している
「脆弱性スキャンの延長」や「導入すれば自動で守ってくれる」といった誤解は、ASMを“ただのツール”に貶めてしまいます。
ASMの本質は、“攻撃者視点で全体の露出領域を把握し続ける”ことにあり、その視点を社内に定着させることが重要です。
2. 対象範囲の設定が不十分
公開中の本番環境だけを見て満足し、開発環境やサブドメイン、クラウド上の放置資産などが見落とされがちです。
特に“誰も見ていない資産”こそ攻撃者に狙われるため、ASMのカバレッジ設定は慎重に行う必要があります。
3. 組織体制や運用ルールが整備されていない
アラートが出ても「誰が対処するか」「いつまでに処置するか」が決まっていなければ、リスクは放置されます。
ASMは複数部門にまたがるため、責任区分や報告フロー、対応KPIを明確にした上で、定常運用に落とし込むことが不可欠です。
4. ツールに依存しすぎて人的判断が伴わない
ASMは“通知”するだけであり、そのリスクの重大性を評価し、行動に移すのは人の仕事です。
アラート疲れやレポート放置を防ぐためにも、分析力と運用体制の両立が求められます。
5. 継続的な改善・見直しがなされていない
一度設定したままの対象範囲やスキャン頻度では、変化し続けるIT環境に追従できません。
ASMは“導入後の改善サイクル”があって初めて機能するため、スコープの再評価やツール設定のチューニング、KPIの共有など、継続的な運用改善が必要です。
これら5つの落とし穴は、いずれも“ASMの技術的な欠陥”ではなく、“組織的な受け止め方と運用設計の問題”です。
したがって、成功の鍵を握るのは「ツールの性能」ではなく、「それをどう活かすかという文化と体制」にあるのです。
ASMは、単なる導入チェックリストで終わらせるものではありません。
それは、企業のセキュリティ意識・IT資産管理・内部統制の在り方を問い直す鏡であり、その問いに答えるプロセスこそが本質です。
ご自身の組織でASMを最大限に活用するためにも、今一度、「なぜ導入したのか」「誰のための施策なのか」「運用は正しく根付いているか」を問い直してみてください。
そこからこそ、本当の“攻撃対象管理”が始まるはずです。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。