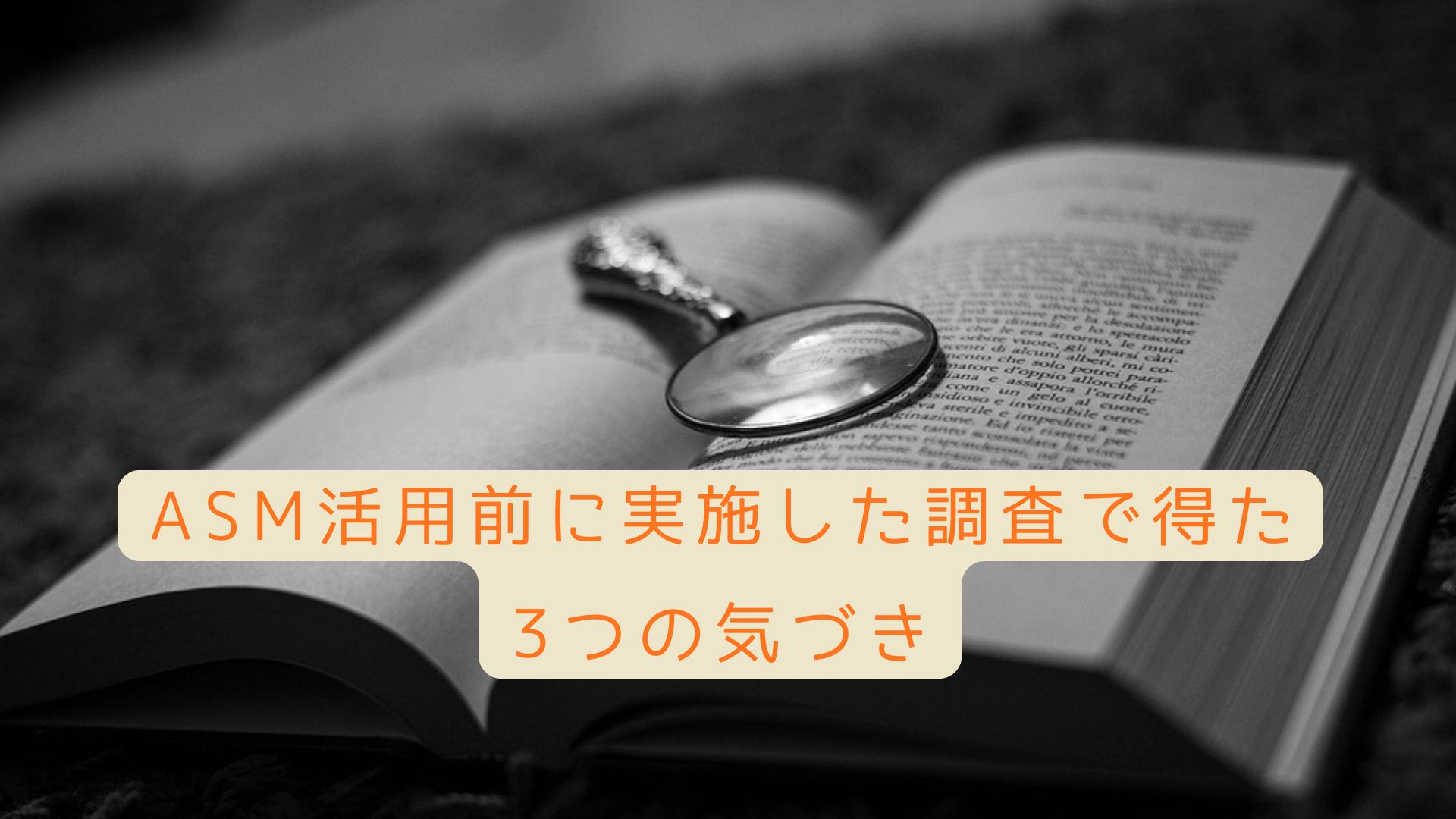企業のIT環境が複雑化・分散化する現代において、サイバー攻撃のリスク管理はますます困難になりつつあります。
とくにリモートワークの普及やクラウドサービスの利用拡大により、社内で把握しきれないIT資産、いわゆる「シャドーIT」が急増しています。
このような背景から注目を集めているのが、ASM(Attack Surface Management:攻撃対象領域管理)という概念です。
ASMは、企業が外部から見えるIT資産の全体像を把握し、潜在的なリスクを洗い出す仕組みとして、近年多くの企業で導入が進められています。
しかし、ASMを導入する前に「どのような調査を行うべきか」「どのような気づきが得られるのか」を明確にしておかないと、せっかくのツールが形骸化してしまうリスクもあります。
この記事では、ASMを本格導入する前に実施した調査によって得られた3つの重要な気づきを中心に、ASMの本質的な意義と導入前調査のポイントについて詳しく解説します。
セキュリティ強化を真剣に検討している企業担当者にとって、有益な気づきが得られる内容となっているでしょう。
ASMとは何か?導入前に知っておきたい基本情報
ASM(Attack Surface Management)とは、企業が外部に公開しているIT資産を洗い出し、それらがサイバー攻撃にさらされるリスクを分析・管理する手法のことです。
近年のクラウド活用やテレワーク推進の影響により、企業のIT資産は拡散し、従来の管理手法では追いきれない状態になっています。
たとえば、以下のような資産が攻撃対象となり得ます。
- 自社Webサイトやサブドメイン
- クラウド上の仮想マシンやストレージ
- パートナー企業との連携API
- 社員が個人管理するSaaSアカウント
これらは一見すると管理されているように見えても、実際には「誰が管理責任者か不明」「アップデートが放置されている」など、セキュリティ上の弱点が内在しているケースが少なくありません。
このような背景から、企業は「自社が外部からどのように見えているか」を常に把握する必要があります。
その手段として登場したのがASMです。
ASMでは、IPアドレスのスキャンやDNS情報の収集、SSL証明書のチェック、Shodanなどの外部検索エンジンの活用を通じて、自社が世界中からどう見られているかを把握します。
この「外部視点」こそが、従来のセキュリティ対策との大きな違いといえるでしょう。
実際、ある企業ではASM調査を行った結果、5年以上前に使用していた旧サービスのドメインが依然としてDNSに登録されており、しかも有効なSSL証明書が残っていたことで、攻撃者に悪用されかけた事例があります。
これは内部では完全に忘れられていた資産であり、ASMがなければ永遠に気づくことがなかったでしょう。
このようにASMは「現在の防御」だけでなく、「過去に存在した資産」までも洗い出し、潜在リスクを包括的に管理する役割を担っています。
導入前に基本的な考え方とスコープを理解しておくことで、その効果を最大限に引き出せるといえるでしょう。
ASM導入前の調査で見えた「攻撃対象領域」の現実
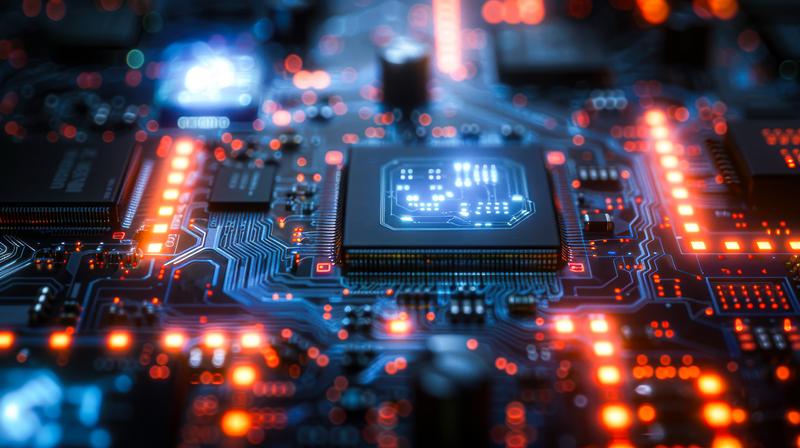
ASM導入前に行った調査により、多くの企業が抱えている「目に見えない攻撃対象領域」の存在が明らかになりました。
表面的には整理されているように見える環境でも、実際には予期せぬリスクが数多く潜んでいたのです。
とくに以下の3点は多くの企業に共通する課題でした。
1. 放置されたクラウド資産の存在
クラウド環境で検証用に立てたインスタンスや、期間限定で公開したサーバーが、その後も削除されずにインターネット上に残っているケースが散見されました。
その多くは、脆弱な設定のまま放置されており、攻撃者にとっては“入り口”として魅力的な存在になっています。
2. 管理されていないサブドメイン
既存のドメイン配下に登録されたまま使われていないサブドメインが、なりすましやフィッシングの温床になっていました。
これは「サブドメインテイクオーバー」という攻撃手法のリスクにつながるもので、ASMによって検出されたことで被害を未然に防げた事例もあります。
3. 野良SaaSの横行
社員が個人的に契約したSaaSサービス(ファイル共有、タスク管理、チャット等)が業務に使われているケースも発見されました。
企業側が把握していないため、IDやパスワードの使い回し、データ漏えいのリスクが潜在化していたのです。
これらの発見は、従来の資産管理手法では見つけ出すことが困難なものであり、ASMという“外部からの目線”がなければ露呈しなかったと言えるでしょう。
重要なのは、こうした問題が「特別な企業」に限られた話ではないという点です。
多くの企業が、日々の業務に追われるなかで、IT資産の棚卸しや管理が後手に回ってしまっているのが実情です。
ASM導入前の調査によって、まずは“自社がどれだけの攻撃対象を抱えているか”を可視化することが、セキュリティ強化の第一歩となるでしょう。
シャドーIT・放置クラウド資産の実態と影響

ASM調査を進める中で、最も深刻なリスクとして浮かび上がったのが「シャドーIT」と「放置クラウド資産」の存在です。
これらは一見、企業活動とは関係ないように見えても、実際には業務の延長線上で生まれた“無許可のIT資産”であり、サイバー攻撃の起点となる可能性が高い要注意領域です。
シャドーITの正体
シャドーITとは、情報システム部門の認知・管理外で利用されているITリソースを指します。
たとえば、以下のようなものが該当します。
- 社員が個人で契約したクラウドストレージ(例:Google Drive、Dropbox)
- 営業部門が勝手に立ち上げたキャンペーン用のLPサイト
- フリーランスが構築したまま報告されていない検証用サーバー
これらは業務上の利便性を優先するあまり、ガバナンスが機能していない典型的な例といえるでしょう。
とくにSaaS利用の急増に伴い、企業全体のIT資産の“見えない部分”が急拡大している現状があります。
放置クラウド資産のリスク
クラウド活用が当たり前となった今、開発プロジェクトごとに一時的なサーバーやDBを構築することも珍しくありません。
問題は、それらがプロジェクト終了後も削除されず、外部に公開されたままになっている点です。
たとえば、ある企業ではAWS上に立てたテスト環境が1年以上放置され、脆弱な認証情報がそのまま残されていた事例が報告されています。
このような放置インスタンスは、コスト面の無駄にとどまらず、標的型攻撃やボットネット感染の初動拠点として悪用される危険があります。
ASMで可視化された“隠れた攻撃面”
ASMは、これらの「見えない資産」を自動的に洗い出し、関係者に通知する仕組みを備えています。
たとえば、DNSレコード・IP範囲・証明書情報・ポートスキャン結果などから、存在すら忘れられていたサーバーやサブドメインを特定することができます。
この“透明化”は、単なる資産管理にとどまらず、「誰がいつ何のために作ったのか」「今も利用されているのか」という“運用経緯の追跡”にも役立ちます。
実際、ASMツールを導入したことで数十件以上のシャドーITが発見され、企業全体のセキュリティポリシーを見直すきっかけになった企業もあります。
こうした取り組みは、結果としてセキュリティレベルの底上げにつながるだけでなく、社内のIT統制やDX推進にも良い影響を与えるといえるでしょう。
ASM調査で気づいた運用体制の“盲点”とは

ASMを導入する前の調査で得られたもう一つの重要な気づきは、**社内のセキュリティ運用体制に潜む“盲点”**の存在でした。
ツールやシステムそのものではなく、「人の運用」「ルールの曖昧さ」「監視の境界線」に問題があるケースが少なくないのです。
部門間で分断された責任領域
多くの企業では、セキュリティに関する責任が情報システム部門に偏っている傾向があります。
しかし、実際にはマーケティングや営業部門が独自に運用しているIT資産も多く、これらの動きを把握しきれていないのが現状です。
たとえば、営業部門が外部委託で作成したLP(ランディングページ)が、契約終了後もドメイン上に残り、SSL証明書が期限切れになっていた例がありました。
このような「情報システム部門の目が届かない領域」がセキュリティホールとなり得るのです。
情報共有の不在と属人化
もう一つの盲点は「情報の属人化」です。
資産の運用状況が一部の担当者の記憶やメール履歴に頼っている状態では、異動や退職のタイミングで管理情報が失われる可能性があります。
ASM導入前に行ったヒアリング調査では、約40%の企業が「過去の資産管理履歴を正確に遡れない」と回答しており、ドキュメント化や中央管理の重要性が浮き彫りになりました。
「やっているつもり」の危うさ
最も見落とされがちなのは、「うちはちゃんと対策している」という安心感そのものです。
とくに、既存の脆弱性診断や定期パッチ運用を行っている企業ほど、「それ以外のリスクがあるとは想定していなかった」と回答する傾向がありました。
ASMの視点は、“外部からどう見えるか”を基準にしています。
つまり、内部ルールの完璧さよりも、「第三者から見て問題がないか」という新たな観点が導入されることで、初めて真のセキュリティ体制が完成に近づくのです。
このように、ASM調査はツール選定だけでなく、運用ルールや組織間連携の再設計にも直結します。
単なるシステム導入にとどまらず、組織全体の意識改革の第一歩として捉えるべきといえるでしょう。
まとめ:ASM導入を成功に導くための調査の視点

ASM(Attack Surface Management)は単なるセキュリティツールではなく、「自社が外部からどう見えているか」を把握するためのセキュリティ運用の起点となる考え方です。
本記事では、ASM導入前に実施した調査によって得られた3つの重要な気づきをご紹介しました。
- 攻撃対象領域が想定以上に広がっている現実
- シャドーITや放置資産による予期せぬリスク
- 運用体制に潜む“見落とされた構造的な盲点”
これらは、いずれも調査を通じて初めて明らかになった課題です。
とくにASMは「攻撃者視点での可視化」を重視しているため、従来の資産管理では見逃されがちな部分を洗い出せる点が大きな特徴です。
また、ASM調査によって得られる情報は、単にセキュリティ対策にとどまらず、以下のような経営的視点にもつながります。
- セキュリティ投資の適正化(本当に守るべき領域の把握)
- DX推進との整合性(クラウド利用の健全性チェック)
- ガバナンス強化(全社的なIT統制の見直し)
一方で、ASMの導入・運用には継続的なリソースと明確なガイドラインの整備が不可欠です。
「調査して終わり」「検出して終わり」ではなく、その結果を元に組織全体で対策と改善サイクルを回す体制づくりが必要です。
そのためにも、まずは導入前の段階で“どのような資産が見えるのか”“どこにリスクがあるのか”を実地調査という形で体感することが最良の一歩となります。
本記事でご紹介した気づきが、貴社のASM導入をより実りあるものにするヒントとなれば幸いです。
自社の攻撃対象領域を「見える化」し、より強固なセキュリティ体制を築く第一歩として、ASMの活用が期待されます。
企業のセキュリティ対策なら「Wit One」にお任せください!

サイバー攻撃の手口は年々巧妙化し、従来の対策だけでは防ぎきれないケースも増えています。とはいえ、専門知識を持つ人材や24時間体制のSOC運用を自社で確保するのは、大きな負担にもなりかねません。
Wit Oneなら、XDRやEDRを活用した常時監視体制を低コストで実現可能。経験豊富なアナリストが、24時間365日体制でインシデントに対応し、ビジネスの安心・安全を支えます。
最小限の負担で最大のセキュリティ効果を得たい企業様は、ぜひ一度ご相談ください。